慶應義塾大学を卒業後、公認会計士として米国現地の監査法人でキャリアをスタートさせ、現在はピッツバーグ大学で電気工学を学ぶフェゼック カルバン氏。その多彩な学びの歩みを、本稿で振り返っていただきます。
このコラムの筆者は5年前まで計量経済学、とくにマーケットデータを活用して機械学習モデルのトレーニングをすることに注目した勉強をしていました。その時期(2016-2020年頃)から普通の学生が扱えるような一般向けライブラリが出てきて機械学習に参入しやすい環境が整いはじめ、価値のあるモデルを自作する感覚が新鮮でこの分野に興味を持ち始めた気がする。それと、経済学は論文で検証されるモデルが直感的(金利差と為替レートとの関連みたいなのを思い浮かべるといいかも)で理解しやすかったのも筆者にとっては魅力的だった。技術系な論文を読んでも専門知識が足りなくてテーマが掴めないことも多いからネ。
卒業してからは、学士で勉強していたことをそのままに会計士として働いていたのだけど、機械学習というツールが広まるにつれ、職場使う水平方向の技術の拡散にとらわれ過ぎて、2022年に一般的となったChatGPTのような大規模言語モデル(以下総括してAIと呼ぶ)のような縦方向の技術の革新に目を向けていなかった。AIのモデルはデータの種類を渡すだけで、おすすめの分析方法を教えてくれるし、自らコードを書かなくてもプログラムの骨組みまで整えてくれる。データと期待する反応を書き込むだけで選択肢をくれるので、これまでそういう情報をインプットしてきてそれを商材(会計事務所で働いていたのでデータ活用と専門知識をまとめたレポートを売っていたようなもの)としてきた身としては、これから先困る。けっしてそのような仕事がなくなるとは言わないが、AIの答え合わせをするような仕事になってしまいそうで、この道はまだ若いうちに諦めなければならないと思い始めた。さらに、AIというのは投資額や利用者数、そして提供されているサービスの数からみて一過性の流行ではなく、PCのソフトウェアのようにこれからも更新され使われ続けるものであることは確からしい。そこで、AIを使う側から作る側になればこれからも食っていけるだろうと思ったが、どうもAIのモデルを開発するのには博士並みの専門知識が必要で20代半ばで勉強を始めたところでなかなか追いつけるものではないことも知った。
じゃあ何か出来ることはないかと思いを巡らせていたら、AIの欠点?としてエネルギー消費量が今あるハードウェアでは大きすぎることに注目しはじめた。AIのトレーニングとインファレンス(ChatGPTに質問を投げた時に起こる膨大な計算量)はそれ単体でかなりのエネルギーを消費するのに加え、それに付随する冷却装置やネットワーク機器もエネルギーを消費する。これに関連して、エネルギー効率の高い集積回路やデータセンターでつかうような電力制御回路を作れるかどうか調べてみるとこれは電気工学(アナログ回路設計)と制御理論、それも修士レベルの知識があればまともな商売ができることが分かってきた。思い立ったが吉日というわけで、仕事後や休日を使い近くのCommunity College (日本でいう専門学校みたいな位置づけ)で電気工学のいろはを勉強していると、今まで自分が触れてこなかった学問から身の回りの機械(PC、電力等)がどのように動いているのが理解できて、これがなかなかに面白いワケ。面白くなってきてテキストを読み漁っていると、今度はTA(Teaching Assistantの略、塾講師のようなもの)として授業、課題のサポート役としてクラスをサポートする役回りにつくことに。内容を分かりやすく伝えようとするとさらに理解度が深まり、最近の論文ではこんなものが設計されているのだなぁと感心したりするほどに電気工学の造詣が深くなっていく。先ほどの話に戻るが、学校にいるだけで横方向の広がりだけでなく縦方向の技術の進歩に興味が出てくる(余談ではあるが、筆者は2019年に言語モデルを制作する講義を学部で履修していて、そのころはこんなモデルがあるのだなぁと思っただけだった。3年後に大規模言語モデルが一般的となったのを見て、思い返せば自分で意識せずとも縦方向の技術革新に触れていたのだと思う)。
そんなのを続けていると、中途半端な知識を得た分、今まで存在さえ認識していなかった分野(半導体の原理など)が増えてきてもっと縦方向の進歩に近づく内容を知りたいと思い始めた。しかし、Community Collegeでは授業内容の深度や設備、教授の専門分野に限りがあり、この知識を仮に仕事として価値提供するようになるにはまだまだ自分の知識と技術に対する慣れが足りないことが分かってくる。自分はリスクジャンキーではなく、どちらかといえばリスク回避主義(会計士になるほどに)で変化を好むタイプではないが、このままではあまりに煮え切らないので徐々に現在の職場から縦方向の先端に身を置く環境に移ってみようと考えるようになっていた。振り返ると興味のある分野に対する知識欲というのは人の原動力としてかなりのウエイトを占めるのではないかと思う。
これが一年ほど続いたのち、職場のサポートや教授の後押しもあり、一旦社会人生活を保留し、現在は大学院に学生として戻っている。課題は多いし、10代後半の頃と違って新しい内容を覚えるのに苦労するし、何かとしんどいこともあるけどなぜかあまり気に病むこともない。これは自分でもまだ分析できていなくて、ゴール(回路設計を仕事にすること)が明確でそれに向かって前進しているのに満足しているのか(口座の貯金額が目標に近づいていく感覚と同じ)、自分が縦方向の技術進歩の先の方に組み込まれている仲間意識があるのか(興味のある方はCompute In Memoryとか調べてみるとイイヨ)、または、経済学からの電気工学のように人と違う道を進むことによる唯一無二感から得られる自己肯定感なのかもしれない(なろう系の主人公のようなものと考えてもらっていい)。だが、結論として後悔はしていないようなので、水平方向の技術の展開に縛られがちな日常業務から解放され、これから先世に出てくる技術に触れる機会のある学校教育に意義を見出しているのは確かである。長々と書いてしまったが、このコラムの読者と学校で学ぶことの意義を考えるうえで、一つの経験談として共有させてもらった。日々使う技術の横方向の広がりだけでなく縦方向の進化を学ぶ機会が教育機関にあると認識してもらえばこのコラムを書いた甲斐があったかもしれません。
フェゼック カルバン
慶應義塾大学経済学部卒業。2020年、米国の監査法人デロイト&トウシュに会計士として入社。製造業における多国籍企業向けの監査に従事。2024年にピッツバーグ大学工学部に入学、電気工学を専攻し、AIインファレンスIC向けアナログ回路設計やメモリ内計算回路(Compute In Memory)の設計に関する研究に取り組んでいる。米国公認会計士。
※内容や肩書は2025年9月の記事公開当時のものです。
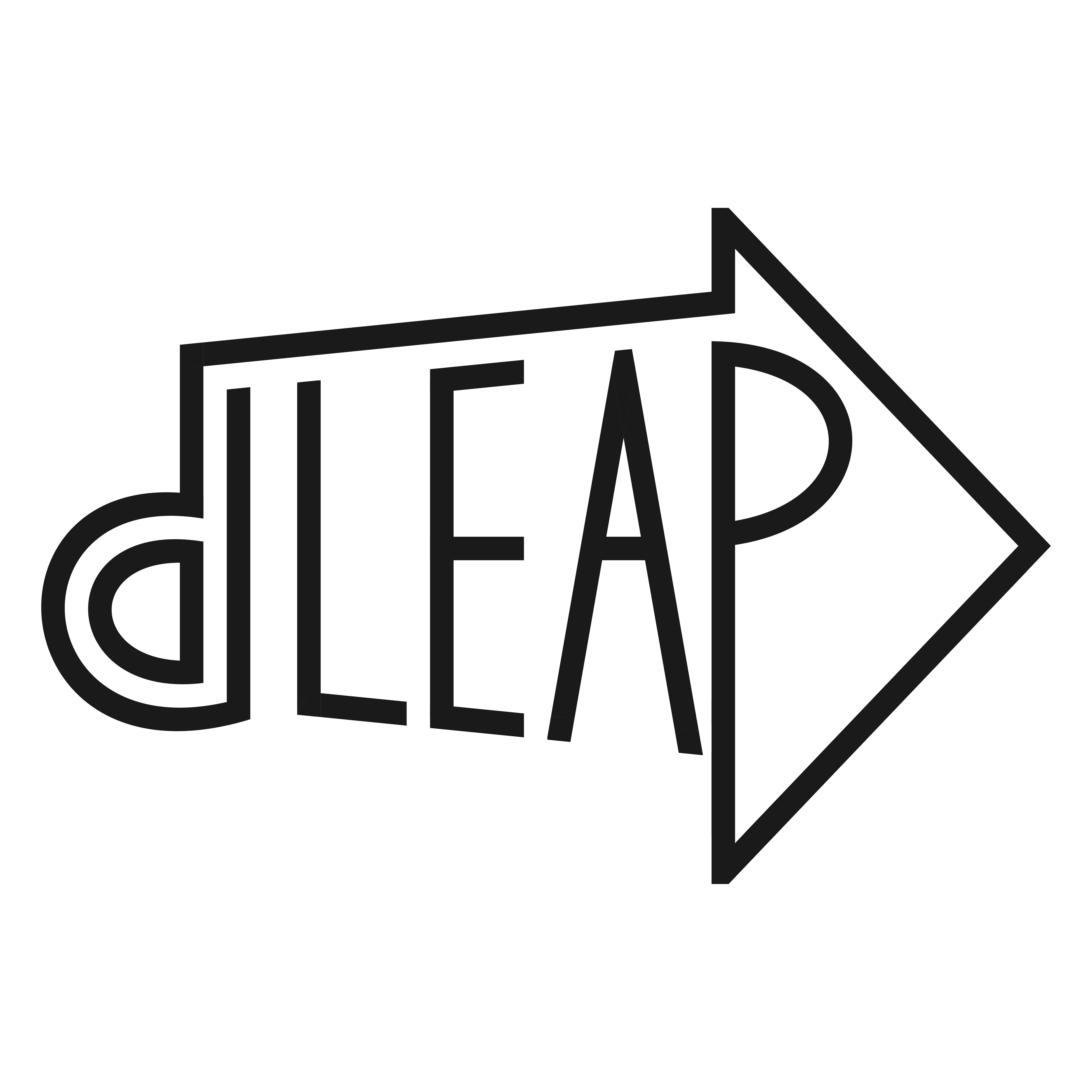

-120x68.jpg)