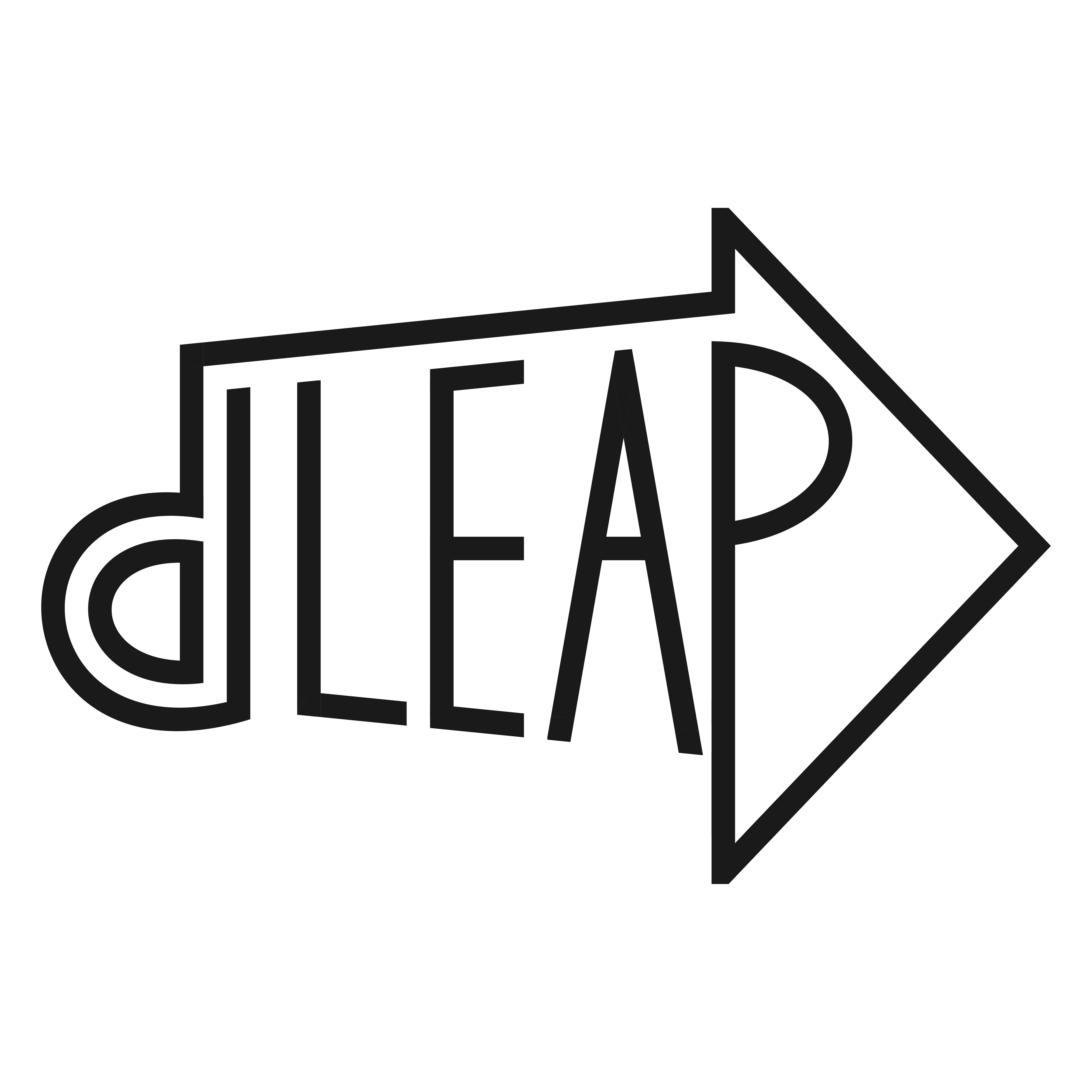はじめに
日本のプライベートエクイティ業界を代表する投資ファンドJ-STAR株式会社を率いる原禄郎氏。慶應義塾大学法学部を卒業後、銀行でキャリアをスタートさせ、シカゴ支店での海外融資業務、アメリカの投資銀行での経験を経て、現在の投資ファンドの世界へと進みました。原氏を含む4名の投資ファンド出身者によって創業されたJ-STARは、現在では運用資産約2000億円を有し、その出資の8割以上を海外投資家が占めています。「課題解決型投資」を掲げ、中小企業の成長支援に注力する同社の代表として、原氏は徹底した結果重視の経営哲学を貫いています。
本インタビューでは、「人の役に立つこと」を軸に据えた独自の価値観を持つ原氏に、ビジネスの本質、真の実力とは何か、そして若い世代へのメッセージについて語っていただきました。
成長の原動力 ー 知的好奇心と学びの機会
ーー 日本を代表する投資ファンドの代表取締役社長として、これまでのキャリアで意識されてきたこと、特にご自身の「成長」にどう向き合われてきたかお聞かせください
成長の根源には「好奇心」があります。私が運営している投資ファンドは、飲食業、製造業、ソフトウェア、物流、ヘルスケア、環境分野など多岐にわたる業種に投資していますが、商業という観点では共通のコンテクストがあります。投資ファンドをやるモチベーションとしては、経済的な成功もないとは言いませんが、私の場合は知的好奇心が大きいです。学歴、職歴に関わらず、驚くほどよくできた事業を構築している方々がいます。そういった事業は(敢えて)世の中に紹介されることを避けている場合も多く、一般情報ではわからない世界の方々に出会い、更に事業を発展させることが知的好奇心の充足であり、本当に学びになります。
ーー 個々人の成長という観点で、投資ファンドでキャリアを積むメリットについて詳しく教えていただけますか
投資ファンドの強みは、投資するたびにその業種の知見や同業他社の動向を含めたあらゆる情報が手に入るという点です。案件実績を積むことで、経営のノウハウが蓄積されます。M&Aに関しても、アカデミックな研究では、成功確率と手がける件数/経験件数が正比例しているというデータがあります。事業会社では本業があり予算も限られているため一般的には行うM&Aの数にも限界がありますが、投資ファンドはそういった制約が少ない。投資ファンドでは多くの案件を経験できるという点でも、競争力を短期に身に付けることができる業界だと思います。
人生の本質 ー「人の役に立つ」という普遍的価値
ーー ビジネスパーソンとして評価される上で、本当に大切なものは何だとお考えですか
私自身は勉強が非常に苦手です。海外のMBAも持っていません。若い方にとって成長というと、肩書きや学歴に走りがちになる場合があると感じます。しかし、実際にはもっとシンプルなものだと思います。人が生きていくということの中には、単純に「人の役に立てば対価を得られる」という構図があると考えています。キャリアや肩書きを大上段に構えるよりも、自分の提供価値が誰にとって一番喜ばれるのかという発想が必要です。
ーー 具体的に、どのように「人の役に立つ」ことを実践されてきたのでしょうか
私はリバタリアンで、とにかく結果重視です。結果を出すためには何をすべきかを考えたとき、結果は誰かが評価するものなので、その評価者が何を求めているかを考える必要があります。転職の際には「自分SWOT分析」をして、自分の強み・弱み・機会・脅威を整理しました。
父親が社会人になったときにくれた本がデール・カーネギーの「人を動かす」で、その本の本質は「まず人の言うことを聞け」ということでした。これは命令に従うという意味ではなく、相手が何を求めているかをしっかり理解しなさいというメッセージです。それが「人の役に立つ」ことの基本だと思います。
ーー 結果を出すことに関連して、キャリアの目標設定について悩む社会人も多いと思いますが、この点についてはどのようにお考えですか
目標設定は人それぞれでいいと思いますが、私はバブル世代の最後の名残で「モーレツ世代」です。スポーツでも「楽しければいい」という人もいますが、私は真剣に勝つか負けるかという中で楽しみが生まれると考えています。勝負に敗れると「悔しい」と表現する場合があると思いますが、それは改善余地が見つかったという意味で、ある種の学びや気づきがあります。私は、真剣勝負自体が楽しいと感じます。あえて今の若い人向けに言うならば、ゲームでハイスコアを出すために色々考えるのと同じで、ゲーミフィケーションの発想で業務目標を捉えるというのもいいかもしれません。私自身は組織や他人への文句はほとんど感じたことがなく、それはスポーツのルールと同じで、仕事とは与えられた制約の中でどれだけ成果を出すかというゲームだと考えています。
J-STAR創業と自己責任の哲学
ーー J-STARの創業時のエピソードを教えていただけますか
創業時におよそ120億円の出資を集めましたが、「サラリーマンだった4人が始めた会社にこんなにお金を預けていただいて大丈夫なのか」という話を創業者間でしていました。一方で、前職では相当な実績を出していた自負があり、業務自体をうまくやる自信はありました。結果を重視するキャリアがあったからこそ独立を実現することができ、信頼も得られたのだと思います。
ーー プライベートエクイティ投資における責任の重さと、それを引き受けることの意味についてどのようにお考えですか
プライベートエクイティ投資では「引き受ける力」が非常に重要です。マジョリティオーナーになるということは、オーナー経営者と同じ立場になるということです。ただ、一般的なオーナー企業と違うのは、投資ファンドとして10年以内に業績を向上させ企業価値を増大させなければならないという約束があることです。自己実現の定義は人によって異なりますが、そういった大きな責任を引き受け、それに応えられたときに「やってよかった」と感じます。果てしなく大きい自己責任をあえて自分に課すことで、自己実現につながるのではと思います。
投資先企業との関わり ー 自立と成長の支援
ーー 投資ファンドとしての成功や達成感はどのようなときに感じますか
投資家の方々に喜んでいただけるよう利益創出に努める一方で、投資ファンドマネージャーとして一番嬉しいのは、当社からの支援を卒業された会社が継続的に成長していることです。中には、当社が投資先の支援から離れた後、瞬く間に業績が傾いてしまう会社もあり、それは大変残念なことです。当社が、業務を通じて、真に自立して成長する企業の礎になれたと実感できた時は非常に嬉しく思います。
ーー 投資先の企業に対して、どのようなスタンスで関わっていますか
私自身の人生観でもありますが、人間個人だけでなく法人も「自立している」ことが重要です。投資先に「投資ファンドの言うことを聞いてください」と言うのではなく、「あなた方自身の問題として、自律的に成長していくために何が必要かを考え、行動していかなければならない」と常々申し上げています。もちろんさまざまな支援を実施しますが、それを命令と勘違いされたくないですし、一方でどうでもいいアドバイスとも思われたくありません。海外に目を向けますと、アジア圏や欧米の投資家は皆、「自己」があるように感じます。激しい競争社会で「自己」を確立しないと生きていけないし、「自己」を確立することで適切なガバナンスやディシプリン/規律が生まれていくのではないかと思います。この仕事では、「市場/市況が悪かったからしょうがない」という言い訳は通用しません。市場/市況が悪いときもあることを想定して、事業を設計しなければならないのです。
今後の展望 ー 積み上げてきた経験を活かして
ーー 今後のビジョンについてお聞かせください
J-STARは自身が立ち上げた会社ということもあり、今後も会社の成長を願っています。私自身のキャリアについては、最初に入行した銀行が破綻し、アメリカの投資銀行でも完全には適合しなかったと感じた経験があります。投資ファンドの世界にその後入ったのは、銀行の破綻やアメリカでのLBOファイナンスの経験が、買収ファイナンスでも活きると考えたからです。自分の将来のキャリアは、自分が必死に積み上げてきたものの延長線上にしかないと考えています。明日から突然違う仕事を始めるのは難しく無駄も多いので、自分の積み上げてきた海外との繋がりやLBOファイナンスの経験を活かせる場所にいることが重要だと思います。
そして、比較優位の観点から、「自分がフルに役に立てる場所」に立っていることが大事だと考えます。今後どのようにして誰の役に立つのかは自分でもわからない部分もありますが、私自身はそのような観点で判断していくのではないかと思っています。
※内容や肩書は2025年10月の記事公開当時のものです。