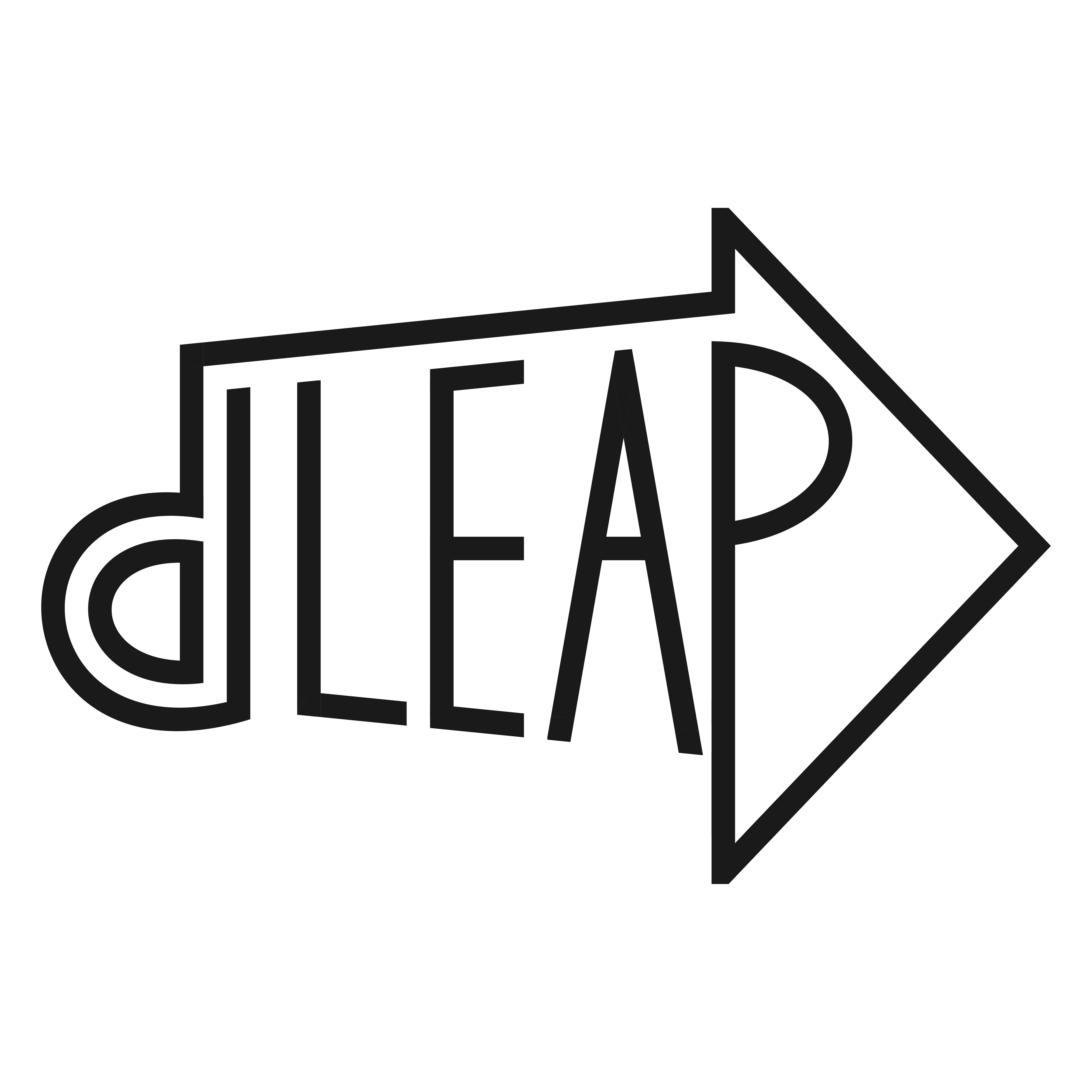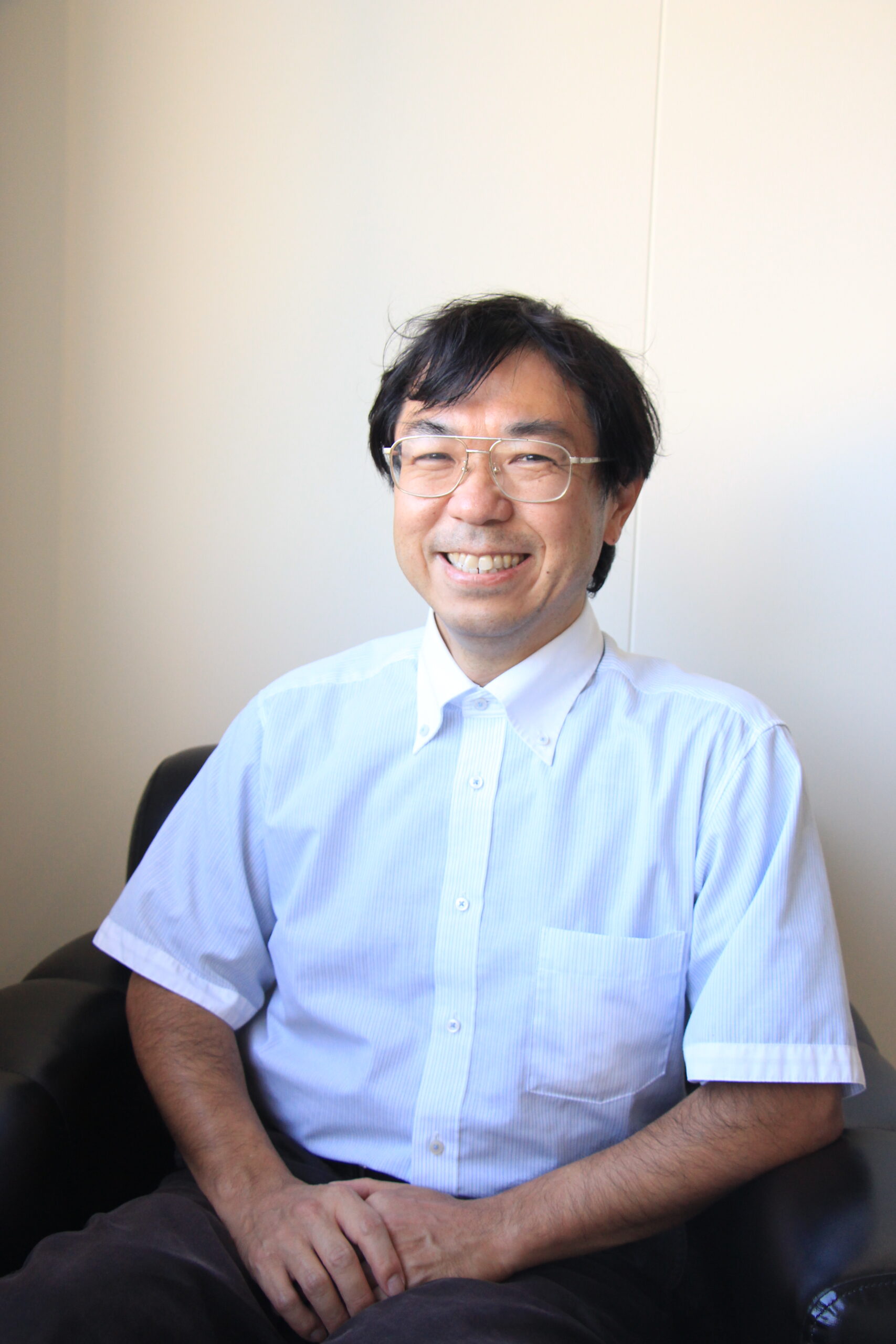はじめに
本インタビューでは、大阪大学を卒業後に九州大学大学院に進学され、独立行政法人 産業技術総合研究所等においてキャリアを積まれた岡山理科大学の牧祥教授にお話を伺いました。現在、大学教授として熱工学や応用物理学の研究に従事する牧教授は、磁場を用いたタンパク質結晶の磁気浮上技術や物性測定技術を組み合わせた独自の研究で賞を受賞されました。
「無駄なことは一つもなかった」と振り返る牧教授。失敗も、回り道も、すべてが今の研究に繋がっているといいます。本インタビューでは、研究者としての豊かな経験を持つ牧教授に、学びの本質、試験の意義、効果的な学習法、そして人生における成長の道について語っていただきました。
教育者としても学生の姿勢に強い関心を持ち、真の学習とは何かを常に考察する牧教授の言葉は、これから学びに向き合う高校生や大学生はもちろん、子どもの教育に悩む親世代、そして学び直しを考える社会人にとっても、重要な示唆に満ちています。
学びの本質 ー 勉強は本当に楽しいもの
ーー 学びを豊かにするという観点で、先生が考える学ぶことの重要性や意義についてお聞かせいただけますでしょうか
今この歳になってつくづく思うのは、勉強というのはとても面白いものだということです。自分の専門分野以外のものに対しても興味があって、定年後は自分の専門とは全然違う分野の研究室に入りたいと思うぐらい、勉強は本当に楽しいものなんです。
ーー 先生ご自身の学びの原点はどこにあったのでしょうか
私の父はすごく良い研究者で、母も教養のある人だったので、小さい頃から「これ何?あれ何?」と質問したときに、常に的確な答えが返ってきました。だから当たり前のように理数系の分野に接してきて、理数系が難しいという発想はなく、ただ単に面白いと感じていました。父は物理学者で高エネルギー加速器研究機構(KEK)や欧州のCERNなどで素粒子の研究をしていました。湯川秀樹先生がノーベル賞を取ったときに感化されて原子核物理学を志したそうです。私も同様に将来は物理の道に進みたいと思っていました。
ーー 勉強の種類と理系分野の魅力について、先生のお考えをお聞かせください
勉強には、人文系の内容や英単語、歴史の年表などを暗記しなければいけないような側面と、理論を理解し応用して問題を解く数学や物理のような側面があります。どちらも大事ですが、個人的には数学や物理の方が面白いと思います。新しいことを発見できるからです。
ーー 理系と文系の違いについてどのようにお考えですか
恩師の一人が言った言葉で「理系と文系の違いは実験をするかしないかだ」というのがあります。結局、考え方や思考プロセスは同じで、一方は実験をして確かめるけど、もう一方は文献を使って調べていくという違いだけで、学問としての根本原理はあまり変わらないのです。
試験と結果の意義 ー 本番で力を発揮することの大切さ
ーー 試験の意義についてどのようにお考えでしょうか
最近、大学で期末試験を無くしてはどうかという話が出ていますが、これにはあまり賛成できません。試験は非常に大事です。なぜなら、一発勝負のときに結果を出すことの大事さを学ぶ意味があるからです。日頃から頑張るのも大切ですが、本番の場で結果を出せるかどうかも重要で、そういったことは試験がないと身につかないと思います。私は「問題が解る」ことと「正解を出す」ことの間には、その背景にとても大きな差があると考えています。「解る」だけではなく「解ける」ようになるためには、さらに一層の努力が必要だと体験的に感じています。だから試験で正解を出せるかどうかは、理解度を測る上でとても大事な評価基準になると思うのです。
ーー 研究において、結果を出すことと長期的な視点をどのように両立されてきたのでしょうか
私が尊敬する先生から言われたのは、「研究は必ず二つの軸を持ってやりなさい」ということです。一つ目の軸は、着実に結果を出せる、簡単なテーマを一つずつやること。もう一つの軸は、結果が出るまで10年ぐらいかかるような大きなテーマをやること。この二つを並行してやりなさいと教わりました。
研究人生から学んだこと ー 無駄なことは一つもない
ーー これまでの研究経験から学ばれたことについてお聞かせください
今思うと、修士課程で恩師に指導された伝熱の研究、博士課程から開始した磁気科学、さらに産総研で開始したタンパク質構造解析といった研究は全て今の自分の研究に繋がっています。2008年頃の話ですが、当時、私が労働安全衛生総合研究所に在職していたとき、医療統計学・疫学を仕事としてやらねばならなくなりました。たまたま統計数理研究所で知り合った高名な先生の指導を受けるために30代後半で一念発起し、仕事をしながら多摩大学の社会人大学院に入学してデータマイニングなどの計量統計学を学びました。その研究で経営情報学の修士号(MBA)を取得したのですが、その後、私は薬学部に8年間も勤務することになって、このときの知識や経験がとても役立ちました。本当に無駄なことは一つもなかったです。私の半生を振り返ると、試験に落ちたり、研究テーマを変えさせられたり、職場環境が激変するなどいろいろ苦労はありましたが、後から見たら全て人生にとって良い転機でした。新しい分野に挑戦するときは、その分野を先にやっているプロを追いかける立場となるので、いつも焦りやストレスが生まれます。そういうときは人と比べず自分がマスターしようと思うことだけを目標にしていくと次第に焦りが解消されていきました。
ーー 先生の研究の成果について詳しく教えていただけますか
もともとは強磁場を使って熱対流を制御する研究から始まりました。つまり上向きの磁気力で重力の効果を相殺して地上で擬似無重力環境を作り、その状態で移動現象を実験と三次元数値計算で解明するという研究です。とても地味な基礎研究でした。ところが磁場を使って物体を浮上させる技術と、修士のときにやっていた熱物性を測る技術(非定常短細線加熱法)を融合させた結果、2016年に良い成果を出すことができ、賞もいただきました。これは単独の技術だけではなかなか難しく、二つを知っていたからこそ融合できたのです。
ーー 失敗や挫折についてはどのようにお考えでしょうか
どんなに頑張っても結果が出せなかったり、うまくいかなかったりすることは誰にでもあります。やるだけやってみて、それでもダメなときは、その道を諦めることは恥ずかしいことではありません。私も大学院受験で合格できなかった経験がありますが、もし最初に受験した大学院に行っていたら、実験的な研究手法はあまり経験できなかったと思います。今となっては違う分野に進んだことがむしろ良かったのです。もし高校入試や大学入試で失敗して落ち込む学生がいたら、「一生懸命頑張ったのにうまくいかなかったなら、その学校とは縁がなかったんだよ。新しいところでしっかり頑張ればいいのさ」と伝えたいと思います。
勉強の本質的な意義 ― 将来に繋がる学びの力
ーー 勉強に取り組む上で、どのような姿勢が大切だとお考えでしょうか
勉強は何かのためにするというよりも、そのときそのとき一生懸命やることが大事だと思います。そうすれば、いつか人生の転機が来たときにそのときの努力が自分を支えてくれます。
ーー 勉強の本質的な意義について、もう少し詳しくお聞かせいただけますか
勉強というのは、将来において仕事をするときに役立つツールであるということを分かってほしいと思います。また、私が高校時代や大学時代で反省点があるとすれば、先生にあまり質問しに行かなかったことです。自分の力で頑張ることは良いのですが、分からないときには人に聞くという努力をもっとすべきだったと反省しています。残念ながら、社会人になると分らないことを教えてくれる善意のある人に会う機会は減ります。今の中高生、大学生たちには、「分からなかったらどんどん先生に聞いていいんだよ、聞くべきなんだよ」ということを伝えたいと思います。
ーー 勉強することで、どのような力が身につくとお考えでしょうか
物事の原因を突き止めていく力がつくはずです。なぜそういう事態になったのかを突き止めるとき、「これは違う、これは正しい」と分類しながら新しい事態を見つけていく過程を通じて、感情を抜きにしてエビデンスに基づいて理論的に考えることを学びます。それは勉強しなければなかなか身につかないものです。また、いろいろな知識や経験を通じて、物事の見方が豊かになります。
効果的な学習法 ー 時間をかけて真の理解を
ーー 効果的な勉強法について、具体的なアドバイスをいただけますでしょうか
時間はかかっても、しっかりと理解することが大切です。昔からある勉強法ですが、教科書をしっかり読んで、なるべく手を動かして声にだしたり、手作りの独自のノートを作成しながら覚えるのが効果的です。また、勉強というのは忘れることを前提にして、復習を繰り返すことが大切です。いくら頑張っても1週間後には半分以上忘れてしまうので、常に復習しながら頭に入れていくことを繰り返す必要があります。この勉強法は時間がかかるので、勉強時間が足りないことに焦りを感じ始めます。私はその焦りが大事だと思っています。何もしていなければ焦りもしませんが、常に勉強していると時間が足りないと感じる。そういう経験が社会に出たときに役立ちます。
ーー 先生ご自身の勉強法について、より具体的に教えていただけますか
私の場合は専門書をしっかり読んで、それを忘れないように復習を繰り返します。また、サブノートを作って部屋中に貼り付けるのが好きでした。覚えたら外していくという方法です。そうすると常に公式や方程式が目に見えるところにあります。今はそんなことはしていませんが、新しいテーマを勉強し始めたらきっとそういう勉強法に戻ると思います。時間はかかりますが、この過程が必要なのです。
ーー 学習において本当に重要なことはなんだとお考えですか
社会に出たら1年浪人したとか留年したというのはどうでもいいことです。むしろ、ちゃんと実力をつけて卒業したかどうかが問われます。だからしっかりした勉強をしてほしいと思います。私個人としては、専門書を読むことをお勧めします。最近、日本の学生はほとんど専門書を読まないので危機感を感じています。要点だけをまとめた本が悪いとは言いませんが、きちんと説明が書かれた本を読む方が本物の実力がつきます。時間がかかっても確実に正解を導ける自分になれるための勉強法にこだわって欲しいです。それを実践するための具体的なテクニックは自分なりの方法を独自に編み出してください。
まとめ ー 若い世代へのメッセージ
ーー 最後に若い世代に向けて、改めてメッセージをお願いいたします
試験のような一発勝負で結果が出るものから逃げてはいけません。厳しいものは厳しいものとして受け止めて、それを乗り越えていく強さが絶対に必要です。そして、勉強は楽しいものだということを知ってほしいです。そのときそのとき一生懸命やっていれば、人生の何かの転機のときにその努力が繋がります。専門書をしっかり読んで、復習を繰り返し、真剣に取り組めば必ず力はつきます。そして分からないことがあれば、どんどん先生に質問してください。それが成長への近道です。
※内容や肩書は2025年10月の記事公開当時のものです。