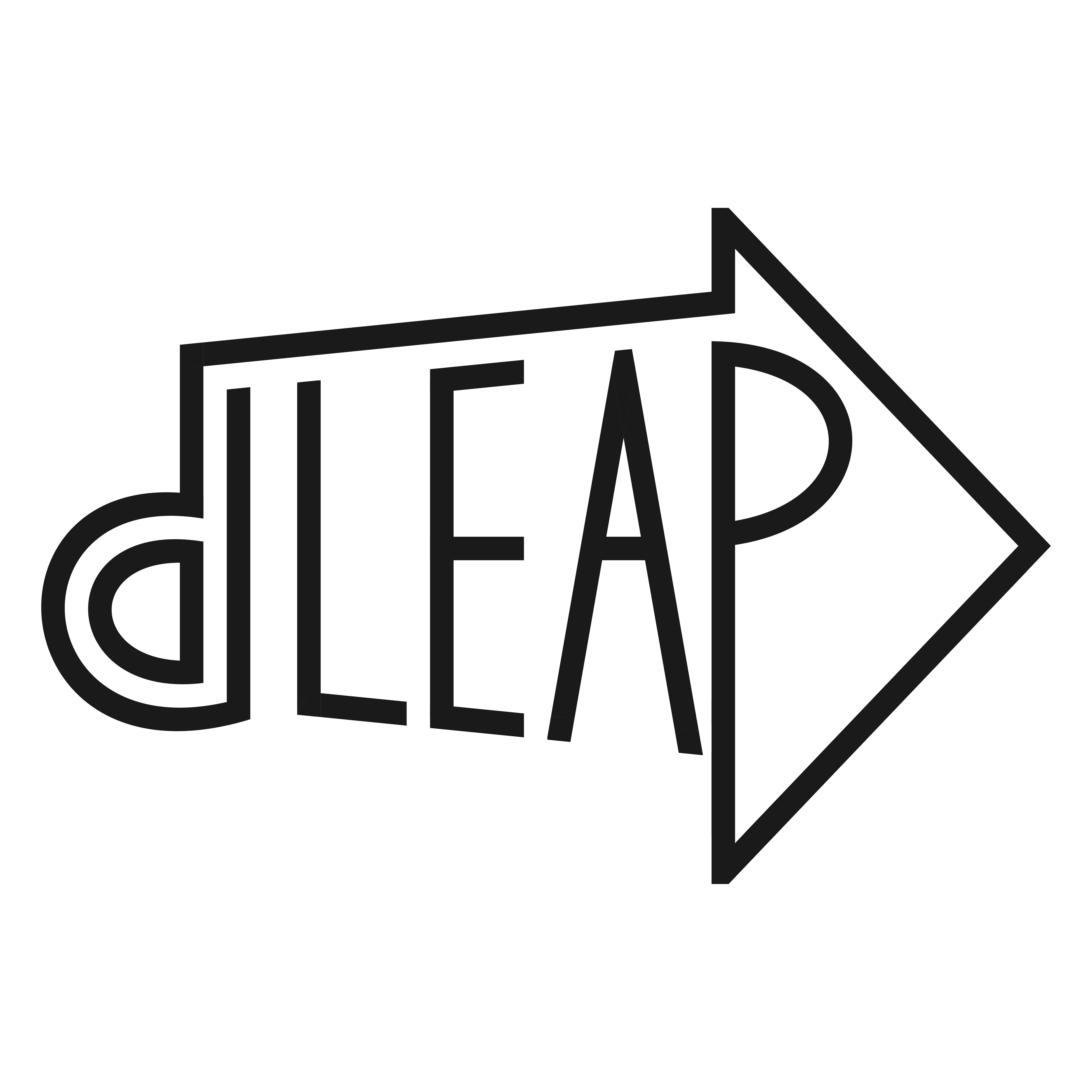はじめに
グローバル化とテクノロジーの急速な進展により、継続的な学習はもはや選択肢ではなく必須のスキルとなっています。学生時代に身につけた知識だけでは対応できない課題に直面し、常に新しい分野を学び続けることが求められる時代です。しかし、多くの人が「どうすれば効率的に学べるのか」「学習のモチベーションをどう維持するのか」という課題に直面しています。
本インタビューでは、シンガポールのインターナショナルスクールで国際バカロレア(IB)を取得し、日本の大学で経済学を専攻、さらに社会人になってからも統計学や米国管理会計士の資格を取得するなど、一貫して学び続けてきた菊本陸氏にお話を伺いました。菊本氏は中学2年生の後半にシンガポールへ移住し、英語がほとんど話せない状態からインターナショナルスクールに適応。大学では経済学を専攻し、特にミクロ経済学、会計、ファイナンス、データ分析に力を入れ、人のコミュニケーションと生産性の関係性に関する研究で優秀論文賞を受賞されました。大学卒業後はグローバルに事業を展開するメーカーで4年間勤務し、現在は建築業界向けに設計AIプラットフォームを提供するスタートアップ企業で活躍されています。
前編では、異文化環境での適応、効果的な学習方法の確立、そして大学での研究活動について、菊本氏の実体験に基づく貴重な洞察をお届けします。
海外経験と国際バカロレア ー 適応と成長のプロセス
ーー これまでの海外経験を含めて、ご自身の経歴についてお聞かせいただけますでしょうか
中学2年生の後半にシンガポールに移って、その後4年間、シンガポールのインターナショナルスクールに通っていました。そこで国際バカロレア(IB)と呼ばれているものを取得して、その後大学で日本に戻ってきて経済学を専攻しました。卒業後はメーカーで4年働いた後に、今は建築業界向けにソフトウェアを提供するスタートアップで働いています。ざっくりそんな経歴です。
ーー シンガポールへの移住は、初めての海外経験だったのでしょうか
0歳から5歳のときに同じシンガポールに住んでいました。ただ、その後はずっと日本に住んでいて、近くの公立の学校で過ごしていました。
ーー 中学2年生という時期に海外のインターナショナルスクールへ移られて、英語の習得はどのような過程を経られたのでしょうか
中2のときにシンガポールに行ったときは、本当に日本の公立中学の英語を勉強しただけというレベルでした。例えば学校のホームルームの先生が「この後、この教室に移動するよ」というような基本的なことも分からない状態でした。最初はめちゃくちゃ大変でしたね。英語の勉強に関しては、日本人がいない環境に耐えて、やはり時間が解決してくれる部分もかなり大きかったと思います。中3、高1と時間を重ねるごとに少しずつ分かるようになっていったという感じです。あとはアプリなどでいろんなイディオムを勉強したりしたのもかなり助けになりました。
ーー 学校の授業で英語に触れること以外にも、ご自身で積極的に学習されていたのですね
はい、素早く反応できる表現の引き出しを広げるために、アプリなどを使って自分でも勉強していました。
ーー 国際バカロレアは勉強量が多いというイメージがありますが、実際にはいかがでしたか
僕自身が実際に比較していないので確かではないですが、勉強量で言うと、日本のいわゆるセンター試験や、大学ごとの試験の勉強量と変わらないんじゃないかなと思います。ただ、大きく違うのは、センター試験は勉強を積み重ねてきたものを当日一発勝負でパフォーマンスを出すのに対して、IBはどちらかというと日々のプレゼンテーションやエッセイなどが30%ぐらいの比重を占めて、最終試験が70%ぐらいの比重で、最終的な成績として合算されます。また、大学への出願時も日々の成績が見られます。アウトプットとして頑張らなければいけないポイントが長いという意味では大変だったかなと思います。
大学での学び ー 興味分野の発見と研究への取り組み
ーー 大学で経済学を専攻されましたが、特に力を入れて学ばれた分野についてお聞かせください
経済学の中でも、マクロ経済学はあまり興味がある得意な分野ではなくて、どちらかというとミクロの経済学の方に興味がありました。それが転じて、会計やファイナンスを深掘りして勉強しました。また、当時データ分析がすごくホットになっていたこともあり、元々数字に関する勉強が好きだったので、経済学と統計学を組み合わせた計量経済学も結構頑張って勉強してきました。
ーー 多くの人は必要に迫られて勉強するものだと考えがちですが、ご自身が好きな分野を見つけるにはどのようなプロセスが必要だとお考えですか
好きな分野や得意な分野は、頑張り続けていたらあるときふとしたきっかけで見つかるものだと思います。僕の場合、中学生のときにシンガポールの学校に入って、英語が全くできない状況でした。英語ができないから他の英語が必要な教科もできなかったという状況の中で、英語ができなくても成績を出せる科目は何だろうと考えたとき、数学を見つけました。数学をきちんと勉強してみたら「あれ、意外と面白いぞ」と気づいたのが大きかったです。頑張り続けて自然に見つかるものなんじゃないかと思います。
ーー 学習のモチベーションを維持することは多くの人にとって課題ですが、どのように継続されてきたのでしょうか
意識せずに頑張れたタイプではなかったですね。頑張れた要因は大きく二つあると思います。一つは自分の行きたい学校や進路を自分で決めたこと。自分で決めると、失敗したときに誰のせいにもできないし、「自分で決めたんだから自分で頑張るしかない」と自分に言い聞かせることができます。もう一つは周りの人の存在です。教えてくれる先生方はもちろんのこと、周りの人が頑張っているから自分も頑張ろうというのは、つられてというわけではないですが、かなり大きかったと思います。
ーー 大学で書かれた論文が慶應義塾大学の「2020 Academic Year Faculty of Economics List of Excellent Graduation Theses」に選ばれたとお聞きしましたが、どのような研究に取り組まれたのでしょうか
所属していたゼミでは、データ分析を中心にいろいろと研究をしていました。経済学部の中で経済学のことをやっていましたが、それ以外にも人事領域(HRテック)のような分野の勉強もしていました。私の論文は、人のコミュニケーションと生産性の関係性を研究するものでした。それをデータ化して、実際に結果がどうなっているのかを分析しました。
ーー 論文のテーマ設定において、どのような視点や基準を持たれていたのですか
論文を書くときに出された条件が「きちんとデータ分析をすること」ということだけだったので、まずそれをクリアするものを見つけようと思いました。経済学から少し離れたところで面白いことができないかなと思ったのと、IoTセンサーなどの普及で定量化が進んだ社会学的な部分において、データをもとに仮説を証明するという経験がしてみたくて、最終的に先ほど言ったようなテーマに落ち着きました。
学びの実践と応用 ー 社会人としての知識活用
ーー 学生時代に学ばれた内容や、学習のプロセスで身につけた経験は、社会人になってから実際に役立っているのでしょうか
学んできた内容で一番わかりやすく役に立っているのは英語です。大学卒業後メーカーで働いていて、海外の部門と話すことも多かったのですが、何不自由なくコミュニケーションが取れたのはかなり大きかったです。また、数学の勉強にも力を入れてきたのですが、メーカーにいるときも様々なものを制御するときに数式を使うことがありました。私は企画の立場だったので、実際に私がやっていたというより技術者の方々に考えていただいていたのですが、その数式を理解しているかどうかで何がどこまでできるのかという理解に関わってくるので、そこで正確な知識は非常に役立ちました。
もう一つの学んできた経験という観点では、メーカーからスタートアップに移った今、LLMのような領域や建築設計など今まで全く勉強してこなかった分野を勉強する必要が出てきています。今まで学習してきたプロセスを積み重ねていることで、同じようなプロセスで勉強しようと考えられるのは良い結果として表れていると思います。
次回予告
後編では、社会人になってからの継続学習、資格取得の実践、転職による新分野への挑戦、そしてAI時代における学びの意義と将来展望について、さらに深くお話を伺います。
菊本 陸
ISS International School (シンガポール)にて国際バカロレア(IB)を取得後、慶應義塾大学経済学部PEARLに入学。2020年に空調を手がけるメーカーに入社し、住宅市場向けの技術戦略立案業務を担当。2025年に建築設計AIプラットフォームを提供するスタートアップへ転身し、建築業界におけるDX化を支援。
※内容や肩書は2025年10月の記事公開当時のものです。