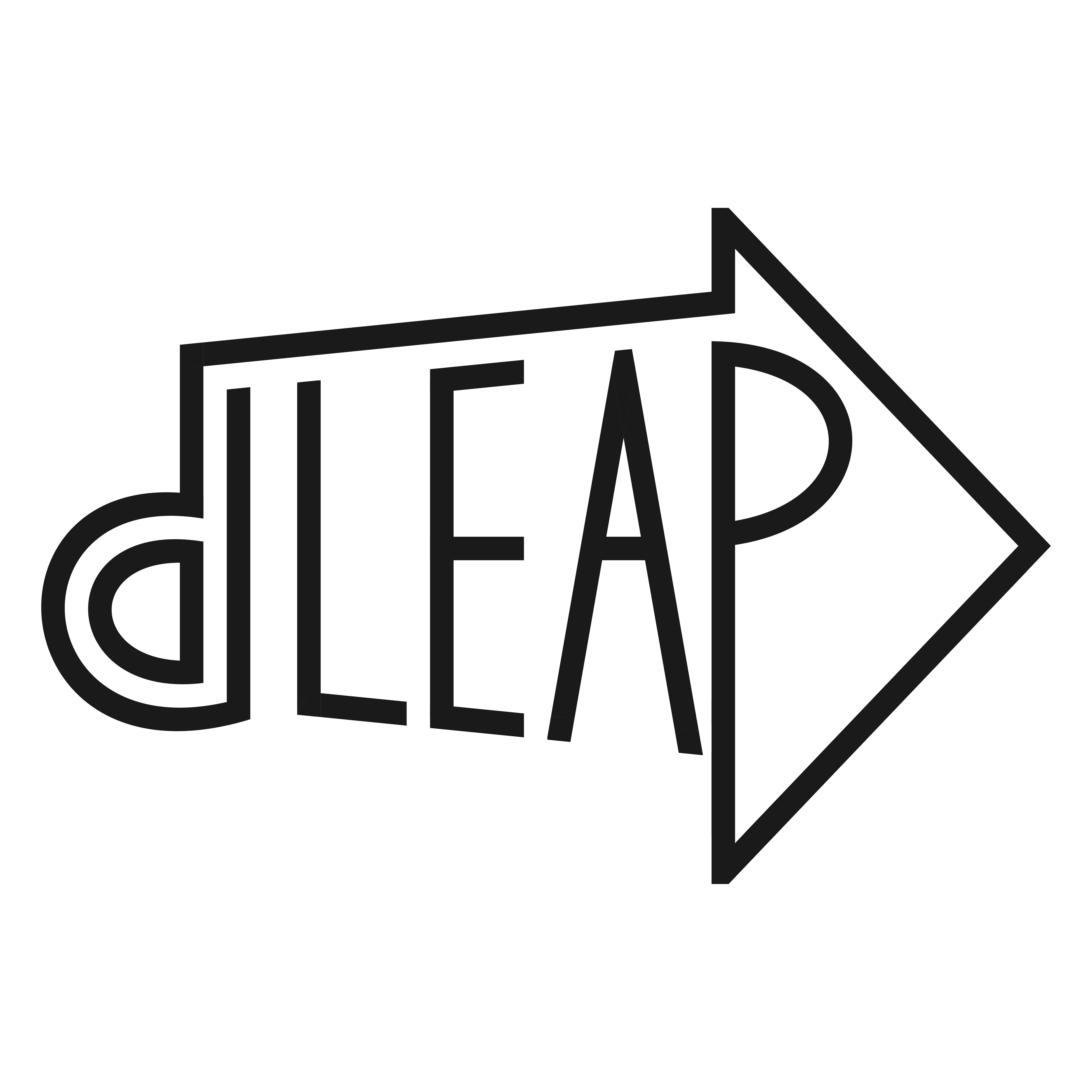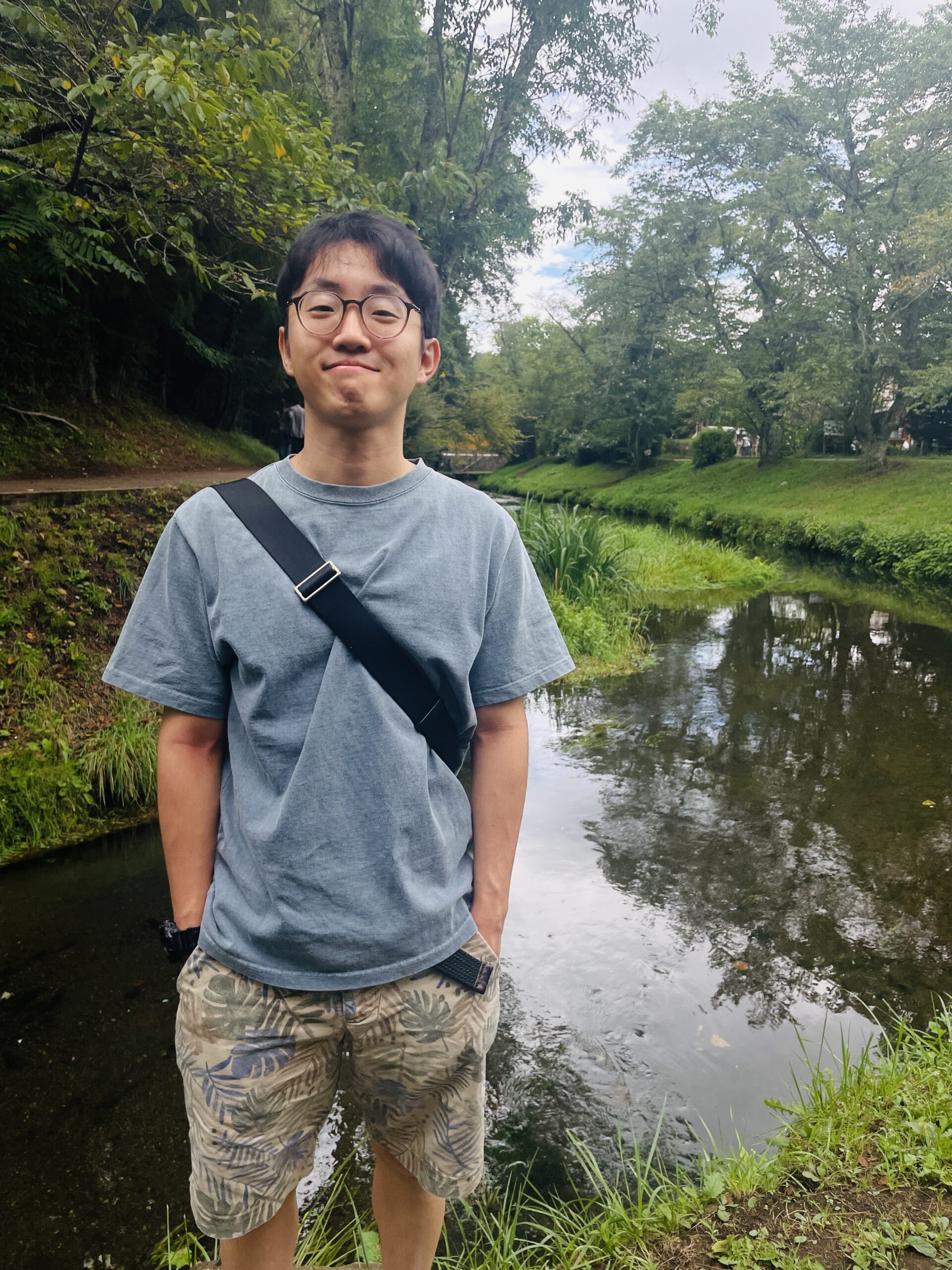はじめに
前編では、シンガポールでの国際バカロレア取得から大学での経済学研究まで、菊本陸氏の学びの基盤形成についてお話を伺いました。後編では、社会人になってからの継続学習、効率的な時間管理の実践、転職による新しい分野への挑戦、そしてAI時代における人間の学びの意義について、さらに深く掘り下げていきます。
統計学や米国管理会計士といった資格を仕事と並行して取得し、メーカーからスタートアップへの転職を経て、現在も建築やLLMなど未知の分野を学び続ける菊本氏。その実践から見えてくる、効率的な学習方法、モチベーション維持の秘訣、そして生成AI時代における人間にしかできない役割について、具体的なアドバイスとともにお届けします。
社会人の継続学習 ー 資格取得と実務への応用
ーー 就職されてからも学習を継続されていますが、具体的にどのような勉強に取り組まれたのでしょうか
就職してからは二つの資格を取りました。一つは統計学の試験、もう一つは米国管理会計士という資格です。
ーー 社会人として働きながら資格取得を目指された動機について、詳しくお聞かせいただけますか
メーカーでの仕事をしているときに、技術戦略立案を担うグループにいました。一緒に働く人たちが技術者や研究者で、彼らは自分たちで物を0から1、1から10とつくっていく中で、自分が貢献できるところを見つけたかったからです。それが一番大きな理由です。もう一つは、数字に関連する勉強が大好きで、問題を解いて正しい答えにたどり着いたときの喜びがゲームをするような感覚に近いです。そういう純粋に楽しいからという理由もあります。
ーー 仕事と学習を両立する上で、時間管理や学習方法についてどのような工夫をされましたか
一つはカリキュラムやシラバスと呼ばれるような、どういうことをしなければいけないのかをきちんと理解して、そこから逆算してインプットをしっかりするということです。もう一つはとにかく問題を解きまくって、自分の弱い部分を特定し、その弱い部分を徹底的に潰していくことです。時間の管理では、試験の日にちを決めてしまって、その日からどういうペースで進めば合格できるかを逆算して考え、日々やらなければいけない量を決めていました。
ーー これまでの学習経験を振り返って、もっと活用すればよかったと感じるリソースや手段はありますか
統計学や管理会計の勉強をしたときはそれほど反省点はないのですが、これまで全体を振り返ってみると、もっと本やオンラインの勉強コースに頼ればよかったと思います。当時はお金をかけたくなくて基本的に教科書を中心に、あとはYouTubeの無料動画やインターネットで調べるだけでした。社会人になってから少しずつでもお金を払って本を買ってみると、めちゃくちゃわかりやすくて、学習の効率が4〜5倍違うんじゃないかと思いました。今はChatGPTなどのツールやオンラインコースも充実しているので、多少お小遣いを削ってもどんどん活用していくべきだと思います。
ーー 学習効率を意識することと、基礎からしっかり積み上げることのバランスについて、どのようにお考えですか
タイムパフォーマンスを意識するのはとてもいいことだと思います。特に社会人として仕事をしながら勉強するのは時間がないのが大前提で、睡眠や健康にも気をつけなければいけません。そういった意味でタイムパフォーマンスを意識するのは非常に重要です。タイムパフォーマンスを意識した結果、「ここがわかっていないな」と気づいた段階で、その課題を潰していくという進め方がいいと思います。
ーー 学習をルーティン化することについて、どのような考えをお持ちですか
なるべくルーティンに落とし込むことを大事にしていました。学生のときはテスト前の徹夜漬けのようなこともありましたが、社会人になって時間がなくなってくるとそれができなくなります。勉強を始めるときにある程度のレールを作って、そのレールをルーティンとしてこなしていく、修行のような感覚でやっていくのが大事だと思います。
また、純粋に今まで解けなかった問題が解けるようになったり、答え合わせをして合っていたり、良い評価をもらえたりしたときの嬉しさをきちんと認識することも大事です。「今楽しいな」ということを自分の中で言葉にしてあげると良いと思います。
新しい分野への挑戦 ー 転職とキャッチアップ
ーー 転職により新しい分野の知識を習得されていると思いますが、どのようなアプローチで学習を進めておられますか
正直、今もキャッチアップ中で、いろいろ模索しながら進めています。キャッチアップする上で気をつけているのは、基本的なところからきちんと積み上げていくことです。例えば建築の領域であれば、建築士の試験向けの本などもたくさんあるので、そういうものを一つ一つ基本的なところから読んでいくことを意識しています。まだまだできていないですが。。
ーー 学習が順調に進んでいる時期と、停滞している時期では、どのような違いを感じられますか
これまでのやり方を繰り返すことで、うまくいっているときは楽になったという感覚があります。一方で、一旦うまくいかなくなると、いろいろと模索しなければならず、そのときはかなりしんどいです。まっさらな状態で何の型もない状態だと模索するのが当たり前ですが、うまくいっているところからうまくいかなくなって模索し直すのはかなりつらいと感じます。
ーー 困難な状況でも学習を継続できる原動力は何でしょうか
仕事を始めてからは、誰かに感謝してもらえることが大きいです。「助かった」や「よく頑張ったね」という褒め言葉をもらったときに感じる幸せのために頑張ってこれたと思います。それがないとかなりきついと感じます。高校のときも、勉強を頑張って結果を出せた際に、周りの人が「教えて」と言ってきてくれて、教えると感謝されるのが嬉しかったりしました。
もう一つは、頑張った分お金をもらえるようになったり、そのお金で美味しい食事や旅行を楽しめたりすることです。自分の欲しいものを手に入れられるというのもかなり大きな理由です。頑張る理由を文字に書き起こしてみると、「こういうものが欲しい」というのがわかるので、つらくても頑張れる理由になります。
AI時代の学びと責任 ー 人間にしかできない役割
ーー 生成AIをはじめとする新しいテクノロジーが急速に発展する中、人間が主体的に学び続ける意義はどこにあるとお考えですか
人間に残されていく役割は「責任を取る」ということだと思います。これは問題が起きたときに非難されるということだけでなく、対策をきちんと説明する説明責任や、法律的な金銭的責任も含みます。責任を取るということは、つまり判断をしたり意思決定をしたりすることです。これらは知識や経験がないとできません。そうなると、日頃からどれだけ勉強しているか、あるいはその勉強したものを活かしてどれだけの経験をしているかが非常に重要になってきます。
ただ、生成AIなどが出てくると、ルーティンワークがなくなってしまい、そのルーティンワークを通して学ぶ経験も減ってきているのが心配です。そういう意味では、今まで以上に勉強の仕方を自分で知ることが求められるようになってきていると思います。
教育観と将来への展望 ー 次世代へのメッセージ
ーー 海外と日本の両方の教育システムを経験されて、日本の教育についてどのような印象をお持ちですか
日本の教育は体系的に学べる良い仕組みだと思います。日本の教育を受けてこられた方々の知識量や、知識に裏付けられた経験は本当にすごいと思います。同時に、日本の教育で感じるのは、せっかく良い知識を持っているのに、それを発信するという点が弱いのではということです。海外の教育を受けてみて、そこさえクリアできれば日本の教育はもっと良くなると思います。
ただ、当然どのような教育にも課題はあります。また、教育システムをすぐに変えられるわけではないので、学校の勉強も頑張りつつ、そこだけにとらわれずにいろいろなコミュニティに参加したり、本を読んだり、オンラインコースを受けたりと、様々なことにチャレンジするのが良いと思います。
ーー 若い世代に対して、学生時代にやっておくべきことについてアドバイスをいただけますでしょうか
私自身、一つの「これが大好き」という分野がある人間ではなかったので、もっといろいろな分野の勉強をしておけばよかったと強く感じます。メーカーで仕事をしているときも、機械のこと、電気のこと、ビジネスのことなど、様々な知識が求められました。仕事をしながらキャッチアップもしますが、基礎がないとキャッチアップの時間も足りません。高校のときに英語や数学だけでなく、特に理科の科目をもっとまんべんなく勉強しておけばよかったと感じます。
ーー ご自身の将来の目標や、どのような人になりたいとお考えか、お聞かせいただけますか
かっこいい大人になりたいと思っています。かっこいい大人とは何かを考えると、日々いろいろな問題が出てくる中で、それをきちんと対処できる人であり、対処する上できちんと自分で決められる人だと思います。そういう大人になるために頑張っていきたいです。
ーー 「かっこいい大人」になるために、日々どのようなことを意識されていますか
結果を出せているかどうかが重要だと思います。それが社会的に認められる結果でなくても、「自分はこれをやって成し遂げた」と言えるものがいくつあるかで、かっこいい大人になれるかどうかが決まってくると思います。結果を出そうとすると、それなりに努力もしなければいけないし、自分の体調や感情のマネジメントもできないといけません。結果を出しているときの喜びをいかに想像できるかが、頑張り続ける上で大事なことだと思います。
ーー 最後に、今後も学び続けていかれるお考えでしょうか
もちろん学び続けたいです。知れば知るほど知らないことが増えてくると言いますが、全くその通りだと思います。むしろ、自分の能力が限られている中で、どういうふうに学ぶ分野を絞っていくかを悩んでいるくらいです。
菊本 陸
ISS International School (シンガポール)にて国際バカロレア(IB)を取得後、慶應義塾大学経済学部PEARLに入学。2020年に空調を手がけるメーカーに入社し、住宅市場向けの技術戦略立案業務を担当。2025年に建築設計AIプラットフォームを提供するスタートアップへ転身し、建築業界におけるDX化を支援。
※内容や肩書は2025年10月の記事公開当時のものです。