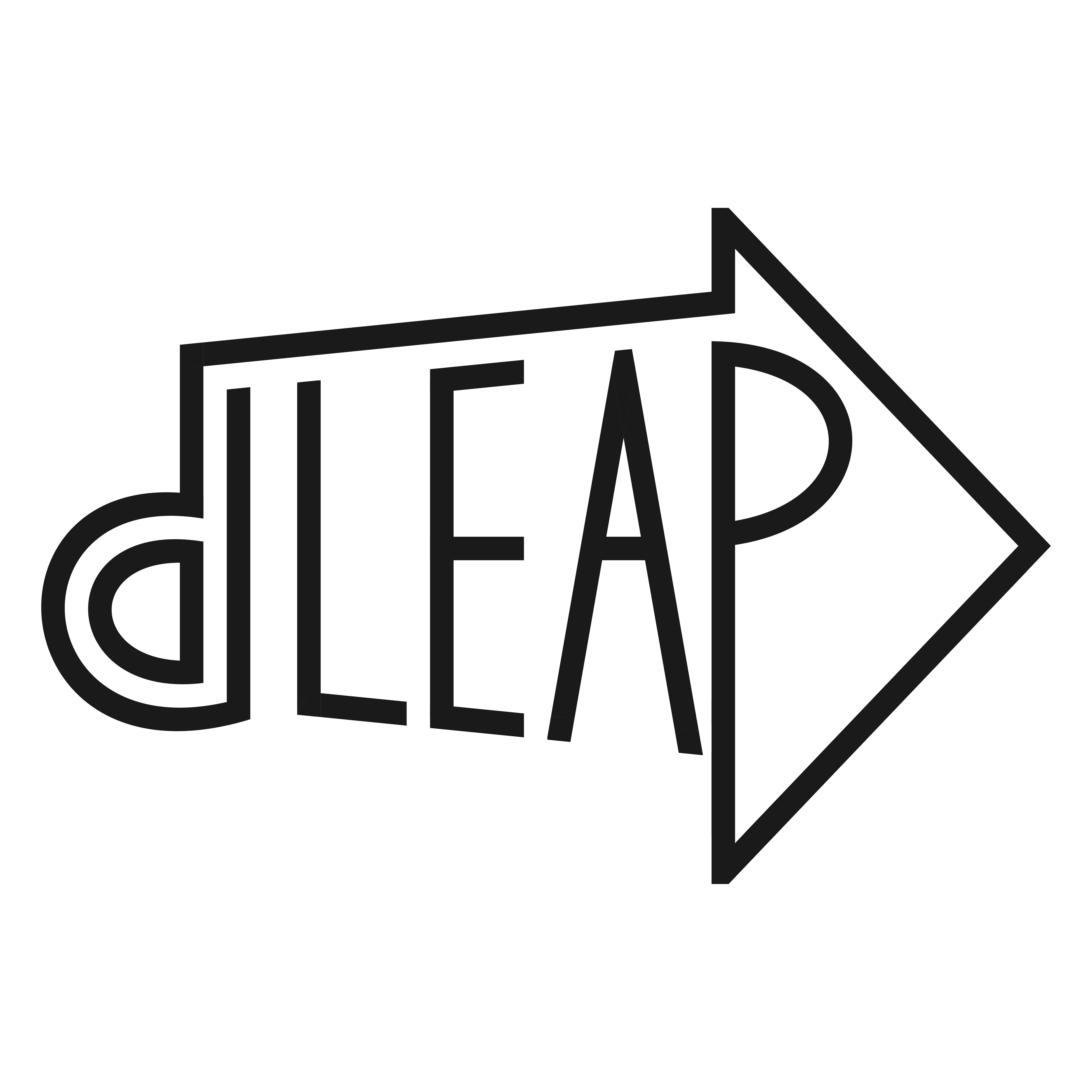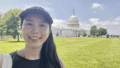総合診療医/家庭医を志す医師の玉井瑛氏が、自身の経験を振り返りながら「学び」の本質を探ります。人の健康を支えるには医学の知識だけでは足りず、人生で経験するすべての出来事が学びになると語ります。そして、どんな時代でも変わらない「困難な状況でも踏ん張る体力(身体的・精神的)」と「他者と協働する力」の大切さについて、若い世代へ向けて考えを綴ります。
大学で医学を学び、現在は総合診療/家庭医療を専門とする医師になるべく研修をしています。
日本ではまだあまり知られていない分野かもしれませんが、総合診療医/家庭医は赤ちゃんからお年寄りまで、臓器や症状に関わらずまず相談に乗り、病気そのものだけでなく「その人の生活」にも目を向ける医師です。
私の医師としての使命は、「医療の専門知識を活かし、多くの人が最期まで自分らしく生きられるように伴走すること」だと思っています。
「病気を治すことじゃないの?」と思う方も多いかもしれません。もちろん、病気を治すことも医師の大切な役割の一つです。ただ、実際には「完全に治る病気」はそう多くありません。薬を飲み続けたり、症状と付き合いながら生きていく人もたくさんいます。
たとえば、高血圧の人は血圧を下げる薬を長く服用しますし、脳梗塞で右半身が動かなくなった人は、その体とともに人生を歩んでいきます。さらに、現代の医学をもってしても原因が分からない痛みや苦しさを抱える人も少なくありません。
もし「病気を治すこと」だけが医師の仕事だとしたら、こうした人たちに何もできなくなってしまいます。「医学的な診断がつかない」「専門外だから」と言って、目の前の人の相談に応えられないことに違和感を覚えた――それが、私がこの道を志した一番の理由です。
この考えの根っこには、小学生のときに通っていた塾で掲げられていた「ノブレス・オブリージュ(高貴なる者の義務)」という言葉があるように思います。
ところで、人々の健康を左右する要因のうち、「医療」が占める割合はどのくらいだと思いますか?
実は、たった2割ほどなのです。残りの8割は、生活習慣(食事・運動・喫煙など)、社会的・経済的な状況(教育・職業・家族など)、そして環境(大気汚染・水質・住居など)によって決まります。
つまり、人の健康を支えるには医学の知識だけでは足りず、幅広い分野への理解が大切になります。机に向かっての勉強だけでなく、人生で経験するすべての出来事が学びであり、それがいつか思いがけない形で活きると私は信じています。
学校教育では、同じカリキュラムに沿って同じ基準で評価されることが多く、気づかぬうちに「点数=自分の価値」と思い込んでしまいがちです。
しかし、社会に出てみると、全員を同じ物差しで測ることはできません。状況によって求められる力や価値はさまざまです。
その中でも、どんな環境でも大切になるのが、「困難な状況でも踏ん張る体力(身体的・精神的)」と「他者と協働する力」だと思います。
前者は、テスト勉強や部活動、行事の準備、習い事や趣味などどんなことでも構いませんが、「難しそうだな」「失敗するかも」と思ったときにあえて挑戦してみる――その経験でこそ得られるものです。
後者は、学生生活の中で自然と身につけられる部分です。他者と関わる中で、自分のコミュニケーションの長所・短所を意識してみたり、気づきをメモしてみたりするのも良い方法です。
テクノロジーが進化する時代でも、このような「人としての基礎力」は変わりません。結局のところ、地道な努力を積み重ねる人がチャンスをつかむのだと思います。
皆さんの未来の可能性は無限大です。
この文章が、ほんの少しでも皆さんの背中を押すことができたら嬉しいです。
玉井瑛 | 医師
中学から慶應義塾一貫校に所属、高校在学中に交換留学1期生として英国Shrewsbury Schoolで1年間を過ごす。帰国後、慶應義塾大学医学部に進学。大学4年生から公衆衛生、総合診療に惹かれるようになり、卒業後は同分野に強い亀田総合病院で初期研修を開始。現在は亀田ファミリークリニック館山家庭医診療科の専攻医として勤務している。
※内容や肩書は2025年10月の記事公開当時のものです。