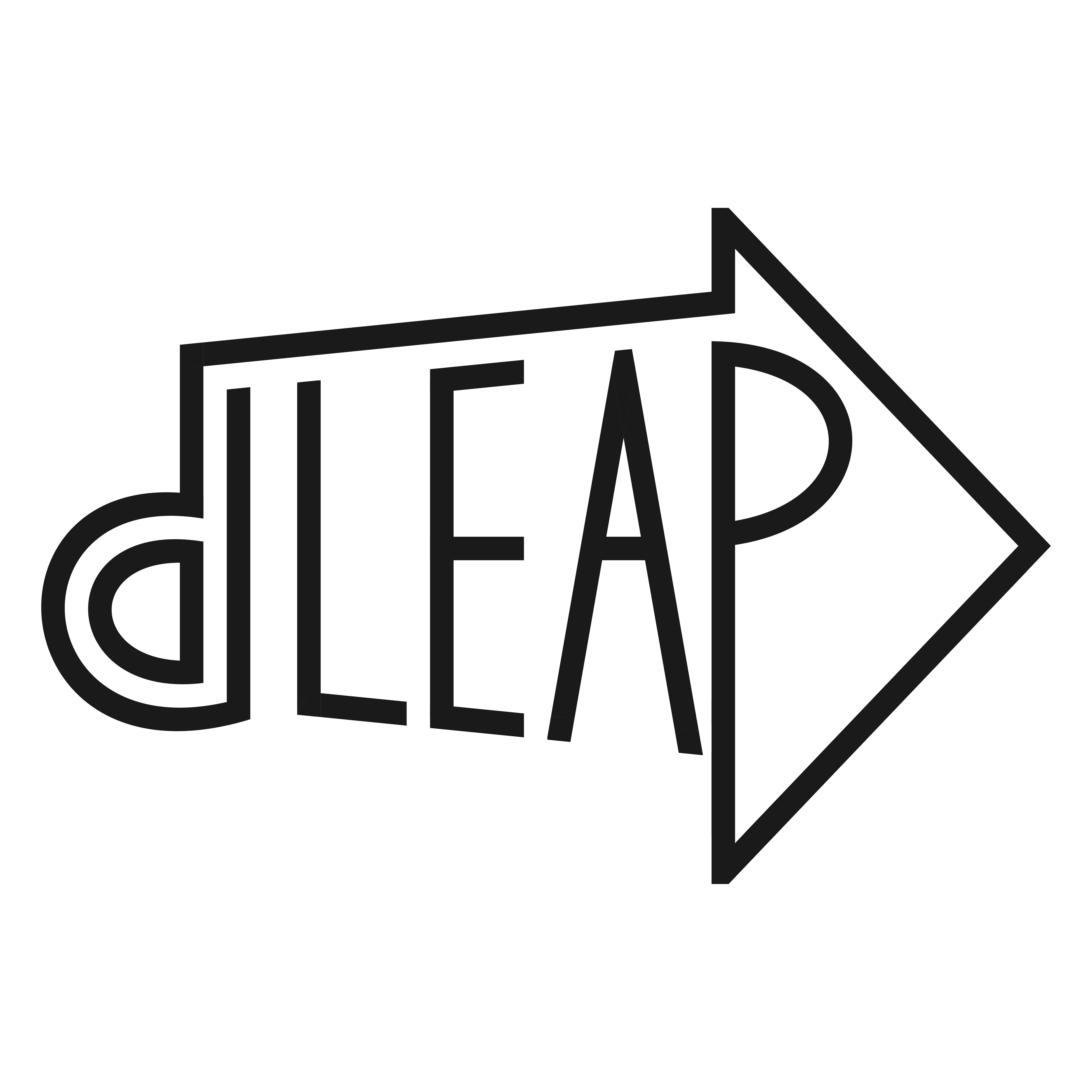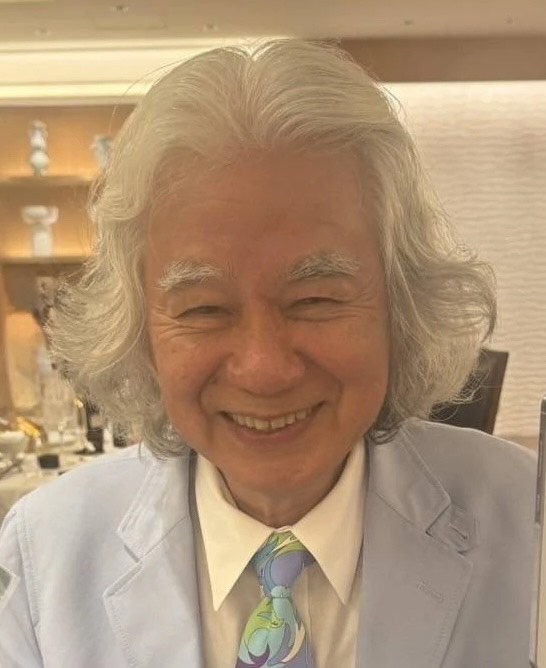はじめに
日本の高度経済成長期から現在まで、半世紀以上にわたってビジネスの最前線で活躍し続ける経営者がいます。本インタビューでは、1969年に中堅建設会社に入社し、団塊の世代の先頭として激しい競争社会を生き抜いてきた柴田透氏に、その豊富な経験と独自の経営哲学についてお話を伺いました。現在も不動産投資事業をはじめ多様なビジネスを展開されている柴田氏は、実践を重視する経営スタイルを貫いています。
「失敗することを前提に考える」という独自の経営哲学、「へこたれない」姿勢の重要性、そして時代の変化に対する柔軟な対応 ー 柴田氏の言葉には、激動の時代を生き抜いてきた経営者ならではの重みがあります。アドバイザーではなく実践者として、今も会社に入り込んで事業活動を主導する柴田氏から、これからのビジネスパーソンへの貴重なメッセージをいただきました。
競争社会からの出発 ー マニュアル化・組織改革・海外展開の軌跡
ーー 柴田さんのキャリアを振り返っていただき、特に思い出深いターニングポイントについてお聞かせいただけますでしょうか
私は団塊世代と呼ばれる最初の年で中学校のクラスが前年の4クラスから13クラス、1クラス60人という大所帯になりました。生まれた時から競争社会でした。会社でも、年功序列ではなく昇格試験による選抜が行われるようになりました。高校受験、大学受験と試験漬けの環境で育ち、会社に入ってからも200人近い同期の中で勝ち抜くために、同級生と勉強会を開くなどの取り組みを行っていました。
当時は「先輩の背中を見て覚えろ」というやり方で現場ごとの個人商店だったように思います。しかし、支店に行った時に各現場でやり方が違い、「このやり方はおかしいのではないか」「なぜこの会社は統一性がないのか」という疑問が生まれました。そこで、現場マニュアルを作ることを提案し、現場で何をすべきか、また、経理や労務の観点からどうすべきか、について検討し、労働監督署への対応や起工式の進め方など、マニュアルを作成しました。その結果、1年後には全国統一の業務のやり方が確立されました。
また、海外事業の拡大にも取り組みました。国内の仕事が減ったとき、新たな柱として海外事業を伸ばしていく必要がありました。上司からの「どうすれば海外を伸ばせるか」という質問に対し、解決策として、米国人弁護士・商社・プラントエンジニアリングの業界で海外実務経験のある人材をスカウトすることを提案し、人材に応じた給与水準を導入し、12人の精鋭を確保し、1年半後に約60億円だった売上がおよそ650億円に伸びました。適材が揃えば事業拡大は実現できると実感しました。
その後は、国内事業と海外事業の第三の柱として新規事業(当時ベンチャービジネスといわれるようになった)を任されました。代々木ゼミナールとビデオ予備校、海外でのレストラン経営、生協とフィリピンでのエビの養殖事業など様々なビジネスに挑戦し、5年目には120億円まで売上を伸ばすことができました。その後、本社へ戻る辞令が出ましたが、事業の面白さが勝り退社して事業をはじめました。
失敗を前提とした経営哲学 ー リスクと成功の考え方
ーー ビジネスの成功に必要な考え方について、どのような要素が重要だとお考えでしょうか
1人でビジネスはできません。「人を惹きつける要素を持っているかどうか」が重要です。アイデアがいくら素晴らしくても、1人では成長に限界があります。効率よく成長するためには、各分野の専門職を揃え、社員の意識改革をしやる気を起こさせる必要があります。
また、「へこたれない」ことも大切です。批判されたときに「この人はわかっていない」と思うのではなく、その意見を反映して改善することが重要です。20年ほど前にスタートアップの創業者と会ったとき、彼らのビジネスプランを見て私は「商売にならない」と言いましたが、彼らは「どこが問題ですか」と聞いてきました。私が指摘した点を1週間後に修正した企画書を持ってきました。その後も、そのようなコミュニケーションを10回ほど繰り返しました。結果的に私も出資し、その会社は上場しました。自己実現に向かい強い意志を持つことも大切ですが、先駆者の意見を聞いて柔軟に計画を修正させていくことも重要です。
新規事業は基本的に「失敗することを前提に考えるべき」です。失敗したら最悪どのくらいの痛手になるのか、出資した方や社員にどのくらいショックを与えるのかを考慮する必要があります。なので、ビジネスプランも一つだけでなく、複数のシナリオを用意することが大切です。最適プラン、死守プラン、最悪プランを想定し、それぞれの対応策を考えておくべきです。多くの起業家は事業が計画通りいくことしか考えていないように感じますが、「絶対」ということはありません。最悪の場合を想定して、どう対応するかを考えておくことが重要です。出資を募る際も「ゼロになることもあることを承知しておいてください」と伝えるべきです。
事業がうまくいきだすと「私には能力がある」と思い込んでしまいがちですが、「事業環境に良い風が吹いていた」だけかもしれません。実際私が関与した会社も、2社が上場したものの倒産しました。失敗から学ぶことは本当に多いですね。そうやって失敗の経験を積み重ねていくことも大切です。
ーー ビジネスを立ち上げる経営者は、事業のリスクについてどのように認識し対応すべきでしょうか
全く新たなビジネス、例えばAIのような分野は本当にハイリスクです。一方、既存のビジネス、例えば寿司屋やラーメン店のようなものは、すでに市場があり、データもあります。「ラーメンを食べる人は1日に何人いるか」というデータがあり、「その5%を獲得できれば商売になる」という計算ができます。某上場飲食チェーンのように「経営者がうちのそばはとびきりうまいわけではない」と認めつつも、科学的なアプローチ、利便性、出店場所などの戦略がしっかりしていれば成功しています。既存市場が確立されているビジネスを現在のトレンドに味付けしたりSNSを利用したりするビジネスと比較すると、何もないところから始めるビジネスはリスクが高いと思います。
またビジネスアイデアを自分だけで評価するのは危険です。商品やサービスを作る側のマインドと買う側のマインドは違います。「これはいい」と思っても、売ろうとしたら売れないことがよくあります。今はメルカリや楽天などのプラットフォームで試せるので、昔よりも楽になりました。昔は店舗をオープンして試すしかなく、最低1年は賃借契約しなければならなかったので、失敗したときのリスクが大きかったです。今は少量生産して試し、反応を見ながら調整できます。無店舗販売ができるのは大きなメリットです。
リスクテイクは必要ですが、リスクをとってはいけないものもあります。例えば、結婚においても「この人とうまくいかなかったらどうしよう」と考え、別れたときにどうするかまで想定しておくべきだと思います。事業も同じで、失敗したらどうやって撤退するかを考えておくことが大切です。日本企業は一度事業を始めたら撤退しにくい傾向があり泥沼にはまることが多いですが、「見切り千両」という言葉があるように、適切なタイミングで撤退する勇気も必要です。撤退すれば次の機会が見つかることは多いです。成功体験に溺れず、常に謙虚な姿勢を持つことも大切です。
現在進行形の挑戦 ー 実行重視の哲学と変わりゆく時代への視点
ーー 今後の展望についてお聞かせいただけますでしょうか
若い人たちと意見が食い違ったり、新しい考え方を理解できなくなったらそれが限界だと思います。また、各事業とも見切りをつけ事業を絞り込んでいます。一方で、新たに始める事業も形にしたいと考えています。私はアドバイザーとして外から助言するよりも、実際に中に入って実行する方が好きです。「こうすればいいね」と言うだけでは動きません。会社に執行役員として入り込んで実際に指揮することが大切だと思っています。
ーー 働き方や価値観など、時代の変化についてどのようにお考えでしょうか
時代はどんどん変わってきています。昔は「会社を休んだら明日は席がない」と言われる時代でしたが、今はフレックスタイムやリモートが当たり前になっています。休みたいときに休み、好きなときに仕事をすればいいというマイペースの考え方です。私も、社員に対して「自分を磨いてください」「ここで何を得て、どこに行くかを常に考えてその仲間つくりをしなさい」と言っています。会社のためでなく自分自身のキャリアを考えることが大切で、結果的には会社にもメリットがあります。他にも、例としては結婚観も変わってきていて「契約結婚」のような形が増えるのではないでしょうか。例えば、「2年契約で、合わなくなったら別れる」というような事例が増える可能性もあると思います。マッチングも流行ってますが、離婚コンサルも面白いビジネスだと思います。本当に時代の趨勢を見ながら、柔軟に対応していくことが大切だと感じます。
※内容や肩書は2025年10月の記事公開当時のものです。