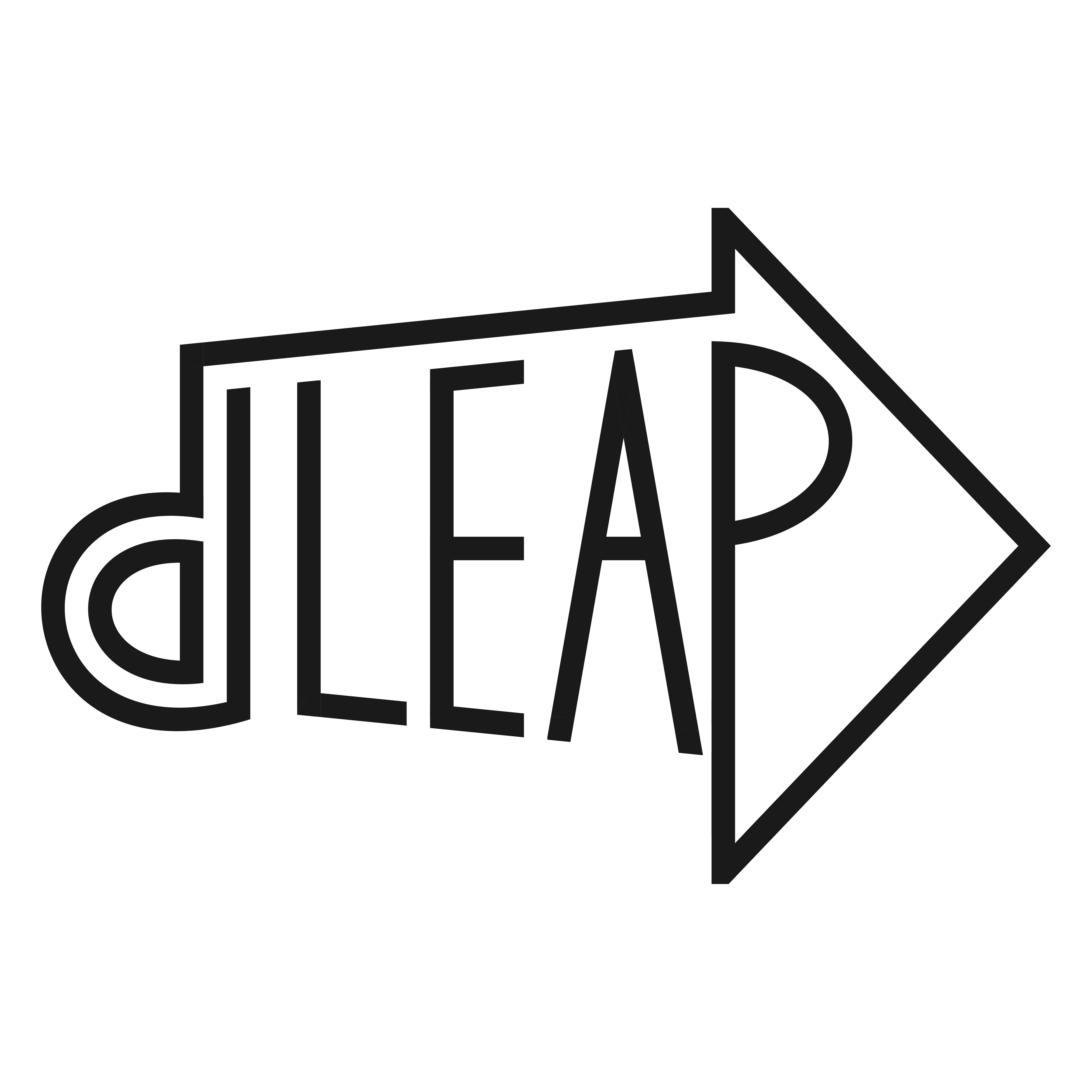医師として働く遠藤龍介氏が、中学受験から医師国家試験まで、自身の学習経験を振り返りながら「勉強」への向き合い方を語ります。「自分が納得すること」「興味を持てること」「ストレスを溜めないこと」という3つのポイントから、効果的な学習法について考察。勉強を通じて得た最大の財産は「友人」だったという、学びの本質的な価値にも触れる体験談です。
みなさんは最近、何か新しいことを学びましたか?
私は最近、2年前に買ったまま放置していたFP3級の本を読み始めました。ChatGPTを試してみたりもしています。あ、そうそう。ナスって炒める前に水にさらしてアク抜きするのが普通なんですね!最近料理を始めて、母からそんな豆知識を教わっています。
今回は、私のこれまでの経験から「勉強」への取り組み方や考え方を簡単にお伝えできればと思います。
中学受験の頃、私は「いい点数をとって上のクラスに行く」ことを目標に勉強していました。算数や理科は得意でしたが、国語は本当に苦手で……記述式の回答や主人公の心情を答える問題に苦戦していました。それでもなんとか第1志望の中学に合格しました。母が一生懸命に語彙を教えてくれたり、単語帳を作ってくれたりしたのを覚えていますが、正直どれくらい効果があったのかはよくわかりません(笑)。
中学・高校はエスカレーター式の学校だったので、学期末ごとの試験がそのまま進路に影響しました。この頃から国語も平均点以上は取れるようになり、大きな苦手意識はなくなりました。理数系も基本的には得意でしたが、時々なぜか平均点ギリギリということもありました。それでも全体を通してまんべんなく勉強することを心がけ、無事に希望の医学部に進学できました。
医学部に入ると、専門的な科目ばかりで「難しい」「頭に入ってこない」と感じることも多々ありました。それでも勉強スタイルは大きく変えず、「身についた知識を増やす」ことを意識しました。たとえば最初に解剖や生理学といった“体の仕組み”を学びますが、それがわかっていないと病気の勉強はそもそも理解できません。いわゆる「その場しのぎ」の知識では太刀打ちできないんです。国家試験の勉強は人生で最も時間をかけた学習でしたが、最後まで大きくスタイルを変えることなく乗り越えることができました。
振り返ってみると、私の勉強スタイルのポイントは「自分が納得すること」だったように思います。
つまり「勉強した内容に自分が満足できるかどうか」です。
算数は理詰めで順番に計算していけば答えに辿り着けます。「ここで計算を間違えた」「この公式を知らなかった」といった形で間違いの原因もはっきりしていて、納得できる。だから学べば次は解ける、という自信につながります。
一方で国語は、主人公の気持ちを30字で答える模範解答を見ても「なるほど」とは思うけれど、小学生の私には本当の意味で理解できませんでした。別の文章が出ればまた違う答えになる。それが国語を難しく感じた理由だったと思います。ただ、中学・高校・大学と進む中で、友人との交流や経験から自然と考え方の幅が広がり、いつの間にか成績も良くなっていきました。
もう一つ大事なのは「興味」です。
勉強しているとどうしても暗記が必要ですが、面白いと感じた内容はスッと覚えられるのに、つまらないと感じたものはまったく頭に入りません。これは科目によっても違うし、先生の教え方次第で変わることもあります。勉強が面白い!と思えれば、ほとんど苦労せず成績が上がるはずです。
とはいえ受験や資格取得のためには、どうしても興味を持てない分野も覚えなければなりません。そんなときは反復あるのみでした。医学の全範囲を扱う問題集を1周し、2周目は間違えた問題だけ、3周目はさらにその中で間違えたものだけ。そうすると覚えにくかった内容も「またこれね」と自然に得意になっていきます。たまに1周目でまぐれ正解して流してしまい、試験で「あれなんだっけ」となることがあったので、少しでも迷った問題は正解していても復習リストに残すようにしていました。
そして最後に大切なのは「ストレスを溜めないこと」です。
私は部活もゲームも睡眠も大事にしていたので、試験前でも制限しませんでした。その代わり「今は勉強しよう」と時間を区切り、メリハリをつけていました。試験の2週間前から勉強を始め、大変そうな科目は3週間前から。直前は間違えた問題や覚えにくい知識だけを確認し、余った時間は普段どおり過ごして試験に臨みました。
例えば「試験前は部活を休んで勉強する」という人もいますが、その時間を100%勉強に使えるかといえば、案外そうでもないと思います。いつになく時間を優雅に過ごしたり、掃除など別のことを始めてしまう場面、ありませんか?むしろルーティンを崩さず、好きなことを続けながら勉強する方が効率的ではないでしょうか。
まとめると、私にとって勉強で大事だったのは
1. 自分が納得できること
2. 興味を持てること
3. ストレスを溜めないこと
この3つでした。
とはいえ人によって「納得できるライン」も「興味を持てる対象」も「ストレスの感じ方」も違います。試験前に徹夜で詰め込む方が合う人もいれば、コツコツ型の人もいます。大事なのは自分や子どもの特性を理解して、それに合った勉強法を選ぶことだと思います。特に子どもは成長とともに考え方が変わっていくので、焦らず見守ることも大切かもしれません。
最後に、「なぜ勉強するのか?」「勉強で得た一番の財産は何か?」と聞かれれば、私は迷わず「友人」と答えます。
勉強を通じて素晴らしい友人に出会えたこと、そして世界が広がったことこそ、学びの最大の喜びでした。
あなたにとって「学ぶこと」はどんな意味がありますか?
遠藤 龍介 | 医師
慶應義塾普通部および高等学校を経て、慶應大学医学部へ進学。高校から水球部に所属し、大学では日本選手権にも出場。
現在はリハビリテーション科医の専攻医として勤務している。患者の疾患・障害を理解した上で、より良い生活を送れるような治療・リハビリテーションや社会サービスを提供し、生活の質を上げることが主な役割。部活動での経験や、様々な患者や家族、医療者との関わりで培ったコミュニケーション力を活かして、教育にも大きく貢献したいと考えている。
※内容や肩書は2025年9月の記事公開当時のものです。