「学びの質を決めるのは、教室の場所でもツールの華やかさでもありません。内発的動機 —これがすべての土台です。」
スタンフォード大学 (Stanford University) で「Stanford e-Japan Program」 のプログラムマネージャーを務めるWaka Takahashi Brownさんは、25年以上の教育者としてのキャリアの中で、紙からデジタルへ、対面からオンラインへと移り変わる現場を見てきました。テクノロジーの進化が寄与するのは「学びやすさ」であり、「学び続ける意思」を点火するのは、いつの時代も学習者自身なのです。
My career in education began over 25 years ago when I first taught at a high school in California. At that time, I did not use many computer-based resources in my classroom. Students turned homework in on sheets of paper, which I graded by hand and returned to them every day. While students did communicate with me via email at times, they mostly talked with me in class or during breaks. After that initial teaching assignment, I changed positions, so my work mainly entailed writing curriculum instead. After several years, however, I once again was tasked with teaching, but this time in an online format.
While I had my initial doubts about how well students would learn without an actual class to physically attend several times a week, I quickly realized that an online education could benefit students in ways that would be difficult with in-person schooling. For instance, students in my first distance-learning class were from many different parts of the country. While we were not able to meet every day, the ease at which we could gather online once a week and exchange ideas was very meaningful. If I had tried to gather these same students in person, it would have been logistically challenging and prohibitively expensive. However, with our online platform, it was convenient and completely free of charge. In-person schooling certainly has some advantages, but the quality of education in both formats depends on students’ internal motivation. In person and online, I am not able to stand over a student to make sure they complete their work or are engaged with it. If the student’s intrinsic motivation is there, both in-person and online formats for learning has proved to be quite effective.
In addition, since my first distance-learning course, technology has evolved so that virtual classes have many functions that enhance students’ experiences and learning. Small discussion groups are formed with ease, and engaging in and monitoring them is much easier than with an in-person class. The audio and video quality for real-time virtual classes has improved significantly as well. Students can raise “virtual hands,” and also share presentations with each other at a click of a button. The benefits of online schooling will no doubt increase as new improvements and methods are discovered.
(日本語訳)
私の教育のキャリアは、25年以上前、カリフォルニアの高校で初めて教えたときに始まりました。当時、授業ではコンピュータを使った教材はあまり用いていませんでした。生徒は宿題を紙で提出し、私はそれを手作業で採点して毎日返却していました。生徒がときどきメールで連絡をくれることはありましたが、やり取りの多くは授業中や休み時間に直接行っていました。その最初の教員任用の後、私は職務が変わり、主な仕事はカリキュラムの作成になりました。しかし数年後、再び教える役割を担うことになり、今度はオンライン形式での授業でした。
週に数回、実際に教室に通う授業がない状態で生徒がどれほど学べるのか、当初私は疑念を抱いていました。けれどもすぐに、オンライン教育には対面では難しい形で生徒に利益をもたらし得ることに気づきました。たとえば、私が最初に担当した遠隔学習のクラスの生徒は、国内のさまざまな地域から集まっていました。毎日会うことはできませんでしたが、週に一度オンラインで集まり、意見を交わすことができる手軽さはとても意義深いものでした。これと同じ生徒たちを対面で集めようとすれば、物流上の課題が多く、費用も現実的ではないほどかかったはずです。しかしオンライン・プラットフォームなら便利で、しかも完全に無料でした。対面の学校教育にも確かに利点はありますが、どちらの形式でも教育の質は生徒の内発的動機づけに依存します。対面でもオンラインでも、私は生徒のそばに張り付いて、課題をやり遂げているか、取り組んでいるかを常時見守ることはできません。生徒に内的な動機が備わっていれば、対面でもオンラインでも学習は十分に効果的であることが分かりました。
さらに、私が最初に遠隔授業を行って以来、技術は進歩し、「バーチャル・クラスルーム」には生徒の体験と学びを高める多くの機能が備わるようになりました。小グループでのディスカッションは容易に編成でき、参加やモニタリングも対面授業よりはるかに簡単です。リアルタイムのオンライン授業における音声・映像の品質も大幅に向上しました。生徒は「バーチャル挙手」ができ、ボタン一つで互いにプレゼンテーションを共有することも可能です。新たな改良や方法が見つかるにつれて、オンライン教育の利点は今後さらに増していくに違いありません。
Waka Takahashi Brown
Stanford Unversity (スタンフォード大学)
Stanford e-Japan プログラムマネージャー
ワカ・タカハシ・ブラウン氏は、スタンフォード大学で国際関係学の学士号(B.A.)および中等教育学の修士号(M.A.)を取得しました。スタンフォード大学国際異文化教育プログラム(SPICE)でのキャリアを通じて、タカハシ・ブラウン氏は教育と日米文化交流の促進に情熱を注いできました。2019年には、米日財団とEngageAsiaから、全米規模のエルギン・ハインツ優秀教師賞を授与されました。国際的なトピックに関する数多くのカリキュラム単元の執筆に加え、タカハシ・ブラウン氏はSPICEのスタンフォードe-Japanプログラムマネージャーおよび春季セッションのインストラクターを務めています。また、タカハシ・ブラウン氏は受賞歴のある児童書作家でもあります。
※内容や肩書は2025年9月の記事公開当時のものです。
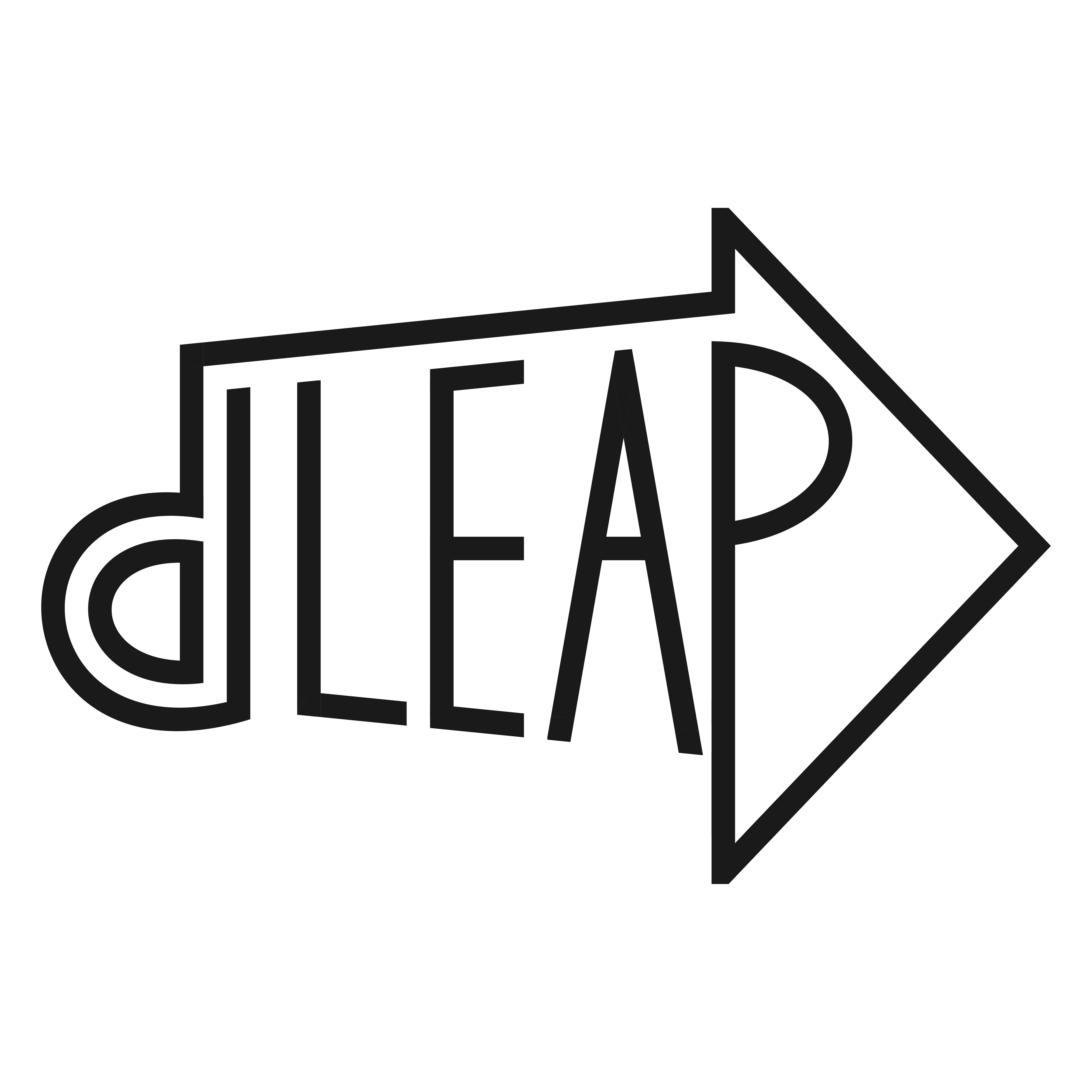
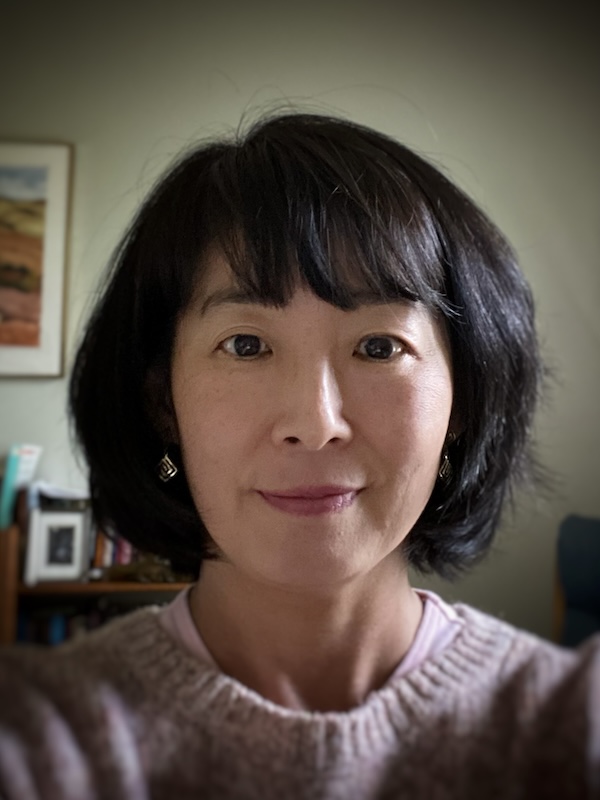
-120x68.jpg)
