薬学教育は過去20年間で劇的な変革を遂げてきました。4年制から6年制への移行、薬剤師の役割の拡大、そして「物から人へ」という新たな薬剤師像の確立―これらの変化は、単なる制度改革を超えて、薬剤師という職業の本質的な再定義を意味しています。かつて調剤室の中で黙々と薬を扱う存在だった薬剤師は、今や患者のベッドサイドで脈を取り、医師のカンファレンスで処方提案を行い、地域医療の要として24時間体制で患者を支える存在へと進化しました。
本インタビューでは、この変革の最前線で革新的な教育を実践している九州医療科学大学の徳永仁教授にお話を伺いました。徳永教授は、全国の薬学部に先駆けて平成18年から患者ロボットを活用したバイタルサイン/フィジカルアセスメント教育を導入し、さらに驚くべきことに、1年以上かけて開発した教材を惜しみなく無償公開するという「教育の民主化」を実践されています。eラーニング大賞文部科学大臣賞をはじめ数々の賞を受賞し、2025年には「みて・きいて・たしかめる!薬学×フィジカルアセスメント」を出版された徳永教授から、現代の薬学教育の特徴、薬剤師に求められるスキルの変化、そしてAI時代における薬剤師の価値について、貴重な洞察をいただきました。
高校生、薬学生、そして現役の薬剤師の方々にとって、これからの薬剤師像を考える上で必読のインタビューです。
6年制薬学教育の現在地 ー 実習と共用試験を中心に
ーー 現在の薬学教育制度について、6年制への移行も含めてご説明いただけますでしょうか
薬学教育は約20年前に4年制から6年制に変わりました。薬剤師国家試験を受けるには、6年制の教育を受けていなければ受験資格が得られません。また、4年次の終わりに共用試験(CBTとOSCE)があり、これに合格しなければ5年次に進級できません。5年次には病院実習と薬局実習がそれぞれ11週間あります。医学部の場合はCBTとOSCEに合格するとスチューデントドクターという肩書きがもらえますが、薬学部ではまだスチューデントファーマシストという制度はありません。その一方、共用試験に合格すると、初めて調剤実習に行くことができ、薬剤師の指導のもとで薬剤師業務を行うことができます。
ーー 薬学教育を行う上での基準やカリキュラムについて、詳しく教えていただけますか
薬学教育は薬学教育モデルコアカリキュラムに従って行われています。以前の考えでは、7割がモデルコアカリキュラムに従い、3割が大学のオリジナルという位置づけでした。薬学教育協議会のウェブサイトで詳細を確認することができます。
ーー 5年次に行われる病院・薬局実習の具体的なスケジュールや内容について、お聞かせください
実務実習は4年次の終わりの2月末から始まり、大きく4期に分けられています。1期11週間、2期11週間、3期11週間、4期11週間という形です。本学の場合は1期から3期までで実習が終わり、4期には実習を行わないようになっています。つまり、2月末から11月初めまでが実務実習期間で、11月中旬からは通常の5年次カリキュラムが再開します。大学によっては5年次は4期まであるところもあり、その場合は2月上旬まで実習があるため、全員参加の授業は5年次にはないという大学もあります。
ーー 実習期間の設定が各大学で異なっているようですが、その背景にはどのような事情があるのでしょうか
人数の受け入れの問題があると思います。例えば、附属病院を持っている大学は自校の病院で実習させることが多いのですが、受け入れ人数に限りがあります。例えば100人の学生がいたとして、1期に受け入れられるのは30人だけという場合、残りの学生は他の期に回ることになります。また、実務実習は、薬局実習から始めなければならないため、病院実習は2期からしか始められないという制約もあります。そのため、全学生が実習を修了するには4期まで使わなければならないという理由で、4期まで実習を行う大学もあります。
「物から人へ」ー 進化する薬剤師の職能と社会的役割
ーー 薬剤師の業務内容は、時代とともにどのような変化を遂げてきたのでしょうか
多くの方が想像する薬剤師の業務は調剤薬局での仕事が中心ですが、病院での薬剤師の業務はあまり知られていません。病院では注射薬の調剤や抗がん薬の調製、治験への参加、ベッドサイドでの薬の説明、血液中の薬物濃度測定などを行っています。約15年前に厚生労働省から「薬剤師を積極的に活用することが可能な業務」として9つの業務が挙げられました。その中に「医師に対して積極的に処方提案を行う」という文言が入り、薬剤師の役割が大きく変わりました。また、「服薬指導の前に患者の状況の把握」という文言も加わり、バイタルサインやフィジカルアセスメントの重要性が高まりました。
ーー 調剤業務の定義や概念にも、大きな変化があったとお聞きしていますが
以前は調剤とは薬剤師が医師の処方箋を受け取って薬を取り揃えることでしたが、現在は「薬剤を交付した後も、その後の経過の観察や結果の確認を行い、薬物療法の評価と問題を把握し、医師や患者にその内容を伝達するまで」が調剤とされています。つまり、調剤はお薬を渡すだけでなく、バイタルサインやフィジカルアセスメントを駆使しながら薬効の評価や副作用のチェックを行い、チーム医療の中で情報共有することまでを含みます。
ーー こうした変化を受けて、現在の薬剤師教育において特に重要視されている理念やコンセプトはありますか
「物から人へ」というキーワードが重要です。以前は薬を扱う業務が中心でしたが、今は人をしっかりと見て、薬を飲む患者さんのフォローアップまで行うことが求められています。副作用や服薬状況のフィードバック、残薬解消、医師への処方提案など、人に焦点を当てた業務が増えています。そのため、薬学教育モデルコアカリキュラムも平成25年に改訂され、令和4年には3回目の改訂が行われました。現在のモデルコアカリキュラムは医師や歯科医師のコンピテンシーとかなり共通したものになっています。
ーー 地域医療の中で、かかりつけ薬局・薬剤師という制度が推進されるようになった経緯について教えていただけますか
この10年くらいの間に、厚生労働省が「かかりつけ薬局」「かかりつけ薬剤師」の概念を推進してきました。以前は処方箋をもらった病院やクリニックの前の門前薬局でそれぞれ薬をもらう形でしたが、かかりつけ薬局・薬剤師を作ることで、自分の薬を一元管理できるようにする方向にシフトしています。薬局も調剤だけでなく、OTC(一般薬品)も置いて処方箋がなくても入れる薬局作りを始めたり、24時間対応できる体制を整えたりと、様々な工夫をしています。
ーー 薬剤師免許取得後の専門性向上やキャリア形成について、どのような制度や変化があるのでしょうか
薬剤師免許を取得した後も、専門薬剤師、認定薬剤師、指導薬剤師などの制度が始まっています。医師と同様に専門性を持つことが求められていますが、薬剤師の場合は全ての領域に渡って知識を有するジェネラリストであることが条件で、その上で専門性を持つことが求められています。各職能団体がこのような認定制度を作り、チーム医療の中で専門性を持って活動することが推奨されています。
患者を診る薬剤師へ ー バイタルサイン/フィジカルアセスメント教育の革新
ーー バイタルサイン/フィジカルアセスメント教育を薬学部で導入されたきっかけや時期について、お聞かせいただけますか
平成22年頃から薬剤師もバイタルサインフィジカルアセスメントのスキルを身につける必要性が高まりました。しかし、本学では平成18年からこの教育を始めています。私は熊本大学病院で薬剤師をしていた時に、医師のカンファレンスで使われる専門用語や数値が理解できず苦労した経験があります。その経験から、薬学部に赴任した際に、共通言語であるバイタルサインフィジカルアセスメントが薬剤師にも必要だと考え、教育を始めました。
ーー バイタルサインとフィジカルアセスメントという用語について、その違いを教えていただけますでしょうか
バイタルサインは脈拍、血圧、体温、意識のことを指します。フィジカルアセスメントはバイタルサインを中心に、視覚、聴覚、触覚を通して評価を行うことです。フィジカルエグザミネーションではなく、アセスメントまで行うことが重要です。
ーー 九州医療科学大学では、バイタルフィジカルアセスメント教育を具体的にどのように実践されているのですか
本学では先述したように平成18年からバイタルフィジカルアセスメント教育を行っており、様々な患者ロボットであるシミュレータを駆使してOSCEの実習を行っています。健康な学生同士のロールプレイでは限界があるため、医学部や看護学部で使われ始めていたシミュレータを薬学教育にも導入しました。4年生、5年生、そして薬剤師の先生方に対しても研修会を実施しています。
-1024x683.jpg)
教育の民主化を目指して ー オープンな教材開発と共有の哲学
ーー 教材開発における九州医療科学大学独自の取り組みや特徴について、詳しくお聞かせください
バイタルサインとフィジカルアセスメント教育の一環として、様々な教材をeラーニングで作成しています。本学の特徴は、作成した教材を外部に公開していることです。多くの大学は自分たちだけで使用していますが、我々はシナリオ作成に1年以上かかるにもかかわらず、全てホームページからダウンロードできるようにしています。また、2年前からは「SCENARIO」という新しいシミュレータを活用し、コミュニケーションまでチェックできるシステムを開発しました。OSCE形式で学生のコミュニケーション行動の有無とアセスメントの正誤を確認できるプログラムを作成し、公開しています。
ーー 高額な教育用シミュレーターの効果的な活用について、どのような方針をお持ちでしょうか
多くの大学では高価なロボット(250万円から300万円)を大事に保管していますが、私はそれは間違いだと思います。ロボットの価値は使われることにあり、壊れるくらい多くの人に使ってもらうべきです。しかし、研修会を行うには教員の時間が取られるという問題があります。そこで我々は「フィジコのフィジカルアセスメント教室」という教材を作り、ホームページからアクセスできるようにしました。キャラクターの「フィジコちゃん」が自動的に説明してくれるので、教員がいなくても学生が自主的に学ぶことができます。この教材はeラーニング大賞の文部科学大臣賞を受賞しました (現在は都合により削除)。
-1024x768.jpg)
ーー 薬学生や薬剤師向けだけでなく、一般市民への教育活動も展開されているとのことですが
薬剤師や薬学生向けだけでなく、一般の方向けにも薬の飲み方や薬についての知識を広めるための教材を作成しています。薬のかるたや4コマ漫画、アニメーションなど、様々な形式の教材を臨床薬学第1講座のホームページにまとめて公開しています。これらの取り組みは医療系eラーニング全国交流会会長賞を受賞しました。また、2025年4月には南山堂から「みて・きいて・たしかめる!薬学×フィジカルアセスメント」という本が出版されました。この本ではQRコードで聴診音などが学べるようになっていますが、内容の多くはYouTubeやホームページでも無料で学ぶことができます。
ーー 貴重な教材を無償公開されている背景には、どのような理念やお考えがあるのでしょうか
本学でのバイタルフィジカルアセスメント教育は私が中心になって行っており、教材の公開も私の判断で行っています。受賞などがあると大学側も喜んでくれます。九州医療科学大学としてはeラーニング教材を作成していることをアピールできますし、我々は営利目的ではないので、広く公開することに問題はありません。これが事業者との考え方の違いです
ーー 今後の教材開発において、どのような展望や計画をお持ちですか
現在はVRを使ったフィジカルアセスメント教育の開発を目指しています。看護用のVR教材はありますが、薬剤師向けのものはまだありません。しかし、事業者からは「投資に見合うリターンが得られない」と言われることが多く、実現は難しい状況です。
これからの時代の薬剤師と求められる人物像
ーー 先生ご自身が薬学の道に進まれたきっかけや動機について、お聞かせいただけますか
元々は工学部の電子工学を希望していましたが、高校で化学、特にベンゼン環の有機化学を学んでから化学の面白さに取りつかれました。将来を考えたとき、資格を取得して活かせる仕事がしたいと思い、薬剤師という免許が取れる薬学部に進路変更しました。
ーー AI技術やデジタル化が急速に進展する中、薬剤師という職業の将来性についてどのようにお考えですか
薬の情報に関してはまだAIには限界がありますが、患者さんのバイタルサインチェックなどはAIが進化しています。例えば、画面上で呼吸数や体温を測定したり、腕時計で心電図を測定したりすることが可能になっています。将来的に触れなくても患者さんの情報が取れるようになれば、薬剤師の役割も変わる可能性があります。しかし、薬剤師の仕事は単なる情報提供だけでなく、処方提案や患者さんとのコミュニケーションなど、人間にしかできない部分も多くあります。
ーー 6年間という長期の教育期間を経て薬剤師になることの意義や価値について、どのようにお考えでしょうか
薬剤師の仕事は昔と比べて大きく変わっています。30年前は、薬剤師は受身の仕事が中心でした。私自身、大学卒業後に病院薬剤師として2ヶ月で限界を感じ、大学院に進学した経験があります。しかし現在は処方提案ができるようになり、薬剤師外来も始まっています。将来的には診察室で医師の横に薬剤師がいて、医師が診断し、薬剤師が処方を提案するような形になるかもしれません。責任は重くなりますが、やりがいのある仕事になっていくでしょう。また、薬学部は入学は比較的容易でも、薬剤師国家試験は難しく、合格するためには相当の知識が必要です。そのため、薬剤師は医師からも信頼される専門職になっていくと思います。
ーー 最後に、これから薬学を志す若い世代へ、メッセージをいただけますでしょうか
以前は薬剤師というと、窓の透明ガラスの向こう側で黙々と調剤をして、薬の説明をして終わりというイメージがあり、コミュニケーションが苦手な方もできる職業と思われていました。しかし、今は「物から人へ」という変化があり、患者さんと接してフォローアップしていく必要があります。高校生が「対人が苦手だから薬学部がちょうどいい」と考えて来ると、現実とのギャップを感じるかもしれません。現代の薬剤師は、病棟でも医師のカンファレンスに参加し、治療方針について意見を求められるなど、コミュニケーション能力が重要になっています。加えて、コミュニケーション能力だけでなく、自分にしかできない専門性を持つことが重要です。私の場合、大学院時代に原子吸光光度計を使った薬物血中濃度を測定する技術を身につけ、それが病院薬剤師時代に役立ちました。自分だけの専門技術があると、それを中心に会話が展開でき、コミュニケーションが苦手でも話が盛り上がります。現在はシミュレータを使った教育が私の主な専門分野になっています。自分にしかできないことを見つけ、それを活かすことが大切です。
※内容や肩書は2025年9月の記事公開当時のものです。
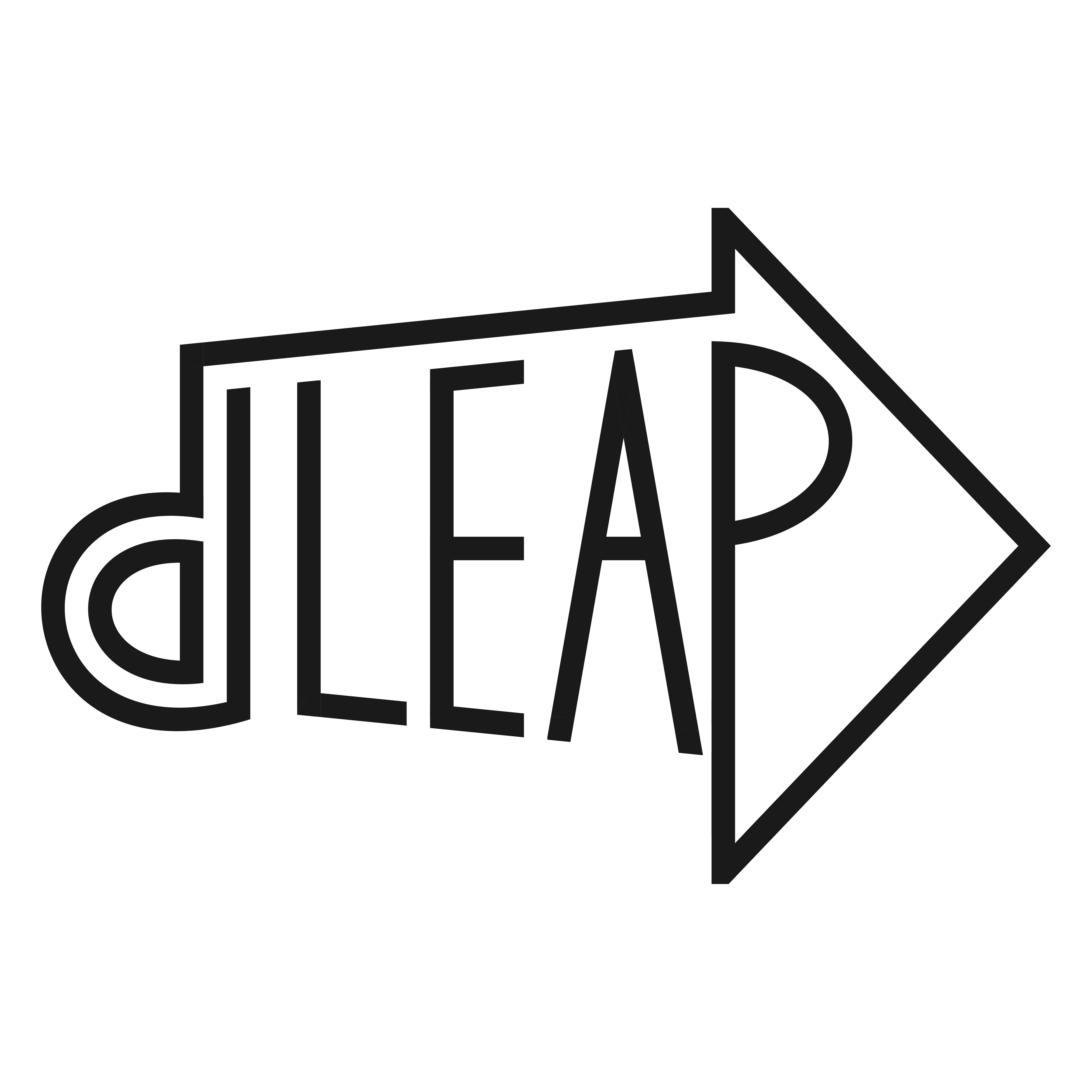
.jpg)

