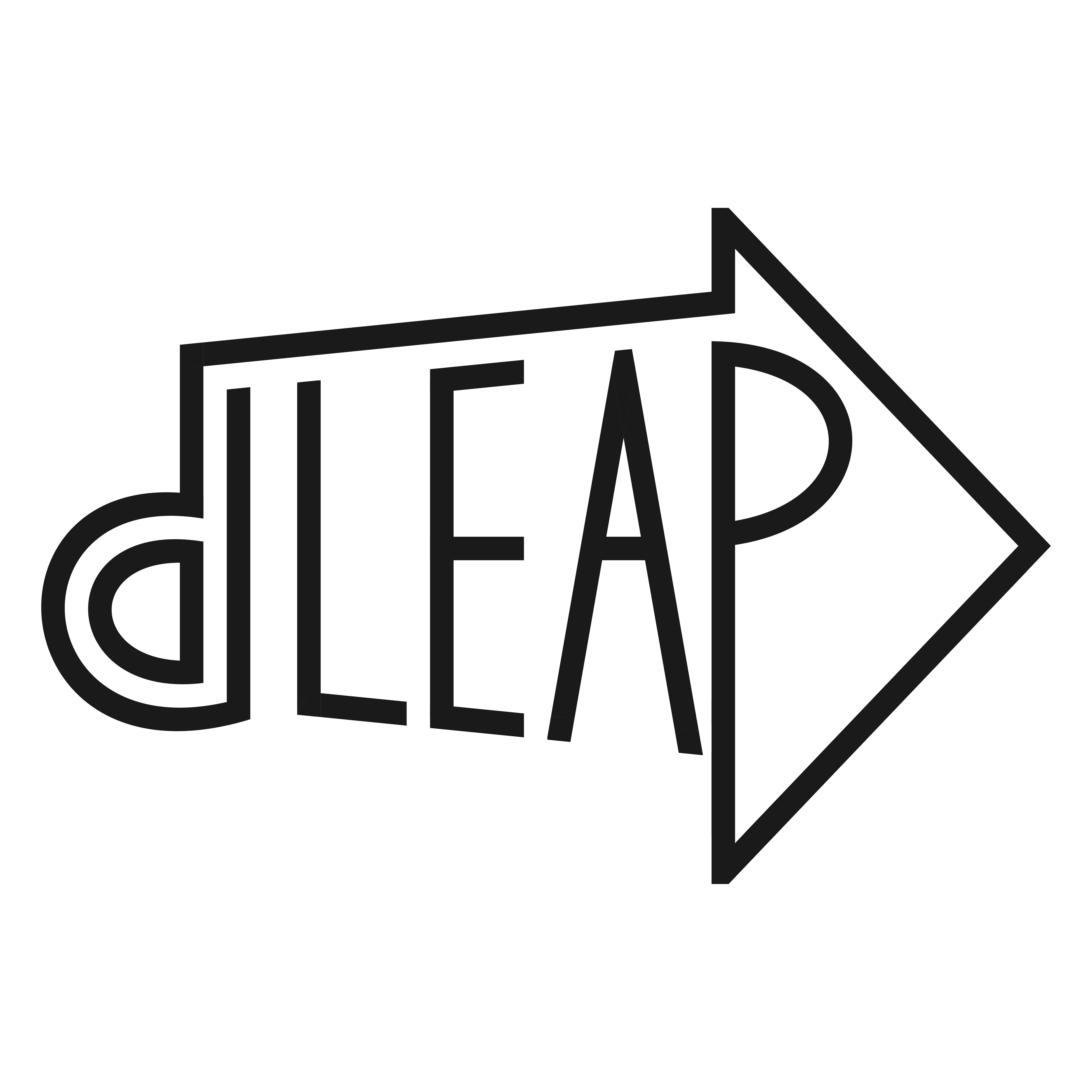早稲田大学政治経済学部を卒業し総合商社にて国内外で活躍する川崎温恕氏が、自身の学習経験を振り返りながら「勉強する意味」を問い直します。
勉強を通じて得られる本質的な価値とは、社会への貢献の仕方に「自分らしさ」を加えられる選択肢を広げることだと語ります。
勉強をする目的は、年齢や教育課程によって変化してきました。
小学校低学年の頃は計算ドリルや漢字練習帳をゲーム感覚で取り組み、小学校高学年になると偏差値で見える勝ち負けに一喜一憂。中学校ではやる気が出ず最低限(笑)、高校では希望する学部に進学するため、大学では興味のある分野を深掘り、そして今は仕事に関連する必要性と、大学時代から続く興味の延長で勉強しています。
その中で、今の自分の思想や思考体系に最も影響を与えたのは、大学時代の学びです。開発経済学という分野に興味を持ち、(経済学の総合格闘技とも言える分野なので)理論系から実証系まで幅広く学び、東アジアの奇跡と呼ばれる経済発展の過程に思いを馳せました。きっかけは何となくの興味でしたが、「資本主義とは何か」「グローバリゼーションとは何か」など、聞いたことはあるけれど理解が曖昧だった概念が徐々に腹落ちしていく感覚が面白く、学んだことが現実世界とつながっていくのが新鮮でした。
そして知識が身についただけでなく、資本主義が生み出す経済成長へのワクワク感や、グローバリゼーションを支える自由主義的な考え方への共感といった、今も変わらない価値観が形成されました。「20歳前後に見聞きし、考えたことは自分の礎となる。だからこそ良質なインプットをし、よく考え、議論しなさい」と語っていたゼミの教授の言葉を、今になって改めて実感します。
大学時代に培った価値観は、今の仕事にもつながっています。もちろん仕事内容にも関係しますが、それ以上に「仕事への向き合い方」に影響しています。例えば、多少大変な仕事でも「この国や市場に少しでも貢献できているかもしれない」と思えると頑張れます。逆にそう思えない仕事は、淡々と粛々と進める感じになります(笑)。
一方で、興味を深め、自分の価値観を形成するための前提となったのは、(中学校で勉強をサボった話はいったん棚上げして)義務教育から高校までの学びだったと思います。数学は論理的・抽象的思考を鍛え、国語は文章を論理的に読み書きする力を養い、理科や社会は世の中で起きている/起きた事象を体系的に理解する力を育て、英語は世界中の情報へアクセスするツールを与えてくれました。得意不得意はあれど(ちなみに私は理科が苦手)、高校までの学習でこれらをある程度身につけられたからこそ、大学での学びにも真剣に向き合えたのだと思います。とはいえ、「その基礎的な勉強がつまらなくてやる気が出ない」という悩みへの明確な解決策はまだ見つかっていません。結局のところ、都度目的を見つけて頑張るしかない、という生成AIに負けそうな回答になってしまいます(笑)。白状すると、中学生の頃は、見かねた親がぶら下げた人参を目当てに勉強していたので、偉そうなことを言っている大人も結局そんなものです。
少し話を飛ばして結論に入ると、皆さんも社会の一員として何らかの形で貢献をしているはずです。その「貢献の方法」に少しだけ自分の色を加えられることこそ、勉強の意味と面白さだと思います(興味がないことを発見する側面も含め)。研究を通じて人類の進歩に貢献する人、美味しい食事を作って人の心と胃袋を満たす人、モノを作ったりサービスを届けたりして社会インフラを守る人、投資で大きなお金を動かす人…など、形はさまざまです。仕事を通じてでなくても構いません。仕事はお金を稼ぐ手段と割り切って、プライベートで社会と関わることでも十分です。ただ、せっかくなら「自分らしい選択肢」を広く持てるように、勉強を頑張ってみるのも悪くないのではないかなと思います。
川崎温恕
早稲田大学政治経済学部卒。2020年に新卒で総合商社に入社。アジアや南米での事業投資を担当し、2023年から2年間インドの投資先に出向。帰国後、引き続き事業投資を担当。
※内容や肩書は2025年10月の記事公開当時のものです。